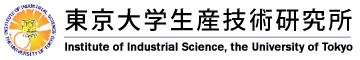~ 以下のプログラムは終了いたしました ~
ご来訪、誠にありがとうございました。
来年も開催いたします。またのお越しをお待ちしております。
講演会プログラム
■ 6月4日(金)
|
| 会場: 生産技術研究所 An棟2階コンベンションホール |
|
| 13:00~13:50 |
「アミノ酸分子をつなげて機能を引き出す」 |
生産技術研究所 工藤一秋 教授
|
タンパク質の構成単位であるアミノ酸やそれがつながってできるペプチドは補助食などとして知られていますが、それらはれっきとした有機化合物であるため、化学者の視点からはこれをつかって機能材料ができないか?という発想に到ります。そのような考えに基づく研究について当グループの成果を中心に解説します。
|
|
| 14:00~14:50 |
「マイクロフルイディクス―デバイスからシステムへ:その進化の過程と将来」 |
生産技術研究所 藤井輝夫 教授
|
ミクロの加工技術を使って作った髪の毛の太さほどの流路の中に液体を入れて、バイオや化学の実験をする技術をマイクロフルイディクスと呼び、流路を作り込んだデバイスをマイクロ流体デバイスと呼びます。本講演では、マイクロ流体デバイスからシステムへの15年にわたる進化の歴史を振り返りつつ、将来の応用展開について考えます。
|
|
| 15:00~15:50 |
「古くて新しいガラスの科学と技術―メソポタミア文明からブループラネットの未来まで」 |
生産技術研究所 高田章 客員教授
|
ガラスの起源は紀元前7000年前と言われていますから、ガラス製品を生活に役立てる研究は人類の歴史とともにあると言っても過言ではありません。日常の生活に欠かせないガラス製品は今後、環境に貢献していくための技術革新が強く求められています。講演ではガラスにまつわる科学と技術をわかりやすく説明したいと思います。
|
|
| 16:00~16:50 |
「実用化する安全運転支援技術―道路と車の連携」 |
生産技術研究所 上條俊介 准教授
|
我が国では、正解に先んじてITSの様々な技術が実用化しています。近年では、道路上の画像等のセンサーやDSRCや光ビーコンの通信を組み合わせて、事故回避の支援を行うシステムが実用化されました。本講演では、路車協調システムを中心とした安全運転支援システムの研究を紹介します。
|
|
| 17:00~17:50 |
「エネルギーインテグレーション―再生可能エネルギー導入+集中 / 分散エネルギーマネジメントの協調 ≒スマートグリッド―」 |
生産技術研究所 荻本和彦 特任教授
|
スマートグリッドは、「時代の要請」と「技術革新」に基づく次世代送電網全般を表す言葉です。本講演では、エネルギーインテグレーションの視点から、スマートグリッドの電力技術としての革新的要素である集中/分散のエネルギーマネジメントの協調を中心に、背景である再生可能エネルギー導入からその実現方法について、議論します。
|
|
| 会場: 先端科学技術研究センター 4号館講堂 |
|
| 10:00~12:00 |
成果発表 |
「第6回 ぼくらは街の探検隊(2010年、渋谷区立上原小6年生×東京大学)
―都市リテラシイの構築と普及―」 |
生産技術研究所 村松伸 教授
上原小学校“街の探検隊”のみなさん
|
小学生と大学院生によるまち探検の成果発表を行います。まちを読み解く力とともに、まちへ還元する力を育みながら、東京の縮景「シブヤ」の中のまち、上原の過去と未来を紡ぎ出します。
|
|
| 会場: 生産技術研究所 An棟3階大会議室(An301.302) |
|
| 15:00~17:00 |
シンポジウム |
| 「バイオやるなら工学だ!!」 |
生研「工学とバイオ研究グループ」10 周年記念シンポ企画委員会
|
| 生研の「工学とバイオ研究グループ」では、工学的なアプローチでバイオ研究に新風を巻き起こしています。本シンポジウムでは、最先端の研究者たちが、これまでの成功の歴史と今後の新展開について熱く語ります。バイオを研究したいが実学やものづくりにも興味のある学生、バイオ研究の産業化を志す企業研究者は必見です。 |
■ 6月5日(土)
|
| 会場: 生産技術研究所 An棟2階コンベンションホール |
|
| 10:00~12:00 |
シンポジウム 「水の知」(サントリー)総括寄付講座 |
「水の知の最前線 襲う水、うつる水、奪い合う水 ~水の脅威に立ち向かう~」
|
| ● 近年の豪雨災害と災害情報を巡る課題 |
静岡大学防災総合センター 牛山素行 准教授
|
| ● 水に潜む小さな難敵-ウイルスと水の安全性を考える- |
東京大学工学系研究科都市工学専攻 片山浩之 准教授
|
| ● 国際河川紛争-水から見える国際政治の裏側- |
総括プロジェクト機構「水の知」(サントリー)総括寄付講座 田中幸夫 特任助教
|
このシンポジウムでは、一般の方を対象に「襲う水」、「うつる水」、「奪い合う水」という3つのキーワードのもと、各分野の水の知の最前線で活躍する3名の研究者からご講演頂きます。私たちが、これからの水の脅威に対して如何にして立ち向かうべきか、皆さんで考えてみませんか?
|
|
| 13:00~13:50 |
「急がば回れの科学―渋滞はなぜ起こるのか―」 |
先端科学技術研究センター 西成活裕 教授
|
「渋滞」は車だけに起こる現象ではありません。人も渋滞しますし、またケータイがつながりにくかったり、工場で在庫がたまったりするのも渋滞です。 さらに我々の体の中にも渋滞があり、それが様々な病気と関係しています。 講演では様々な渋滞を考察しつつ、その解消法について、いろいろな映像を交えて科学してみたいと思います。
|
|
| 14:00~14:50 |
「ロボット時代の創造」 |
先端科学技術研究センター 高橋智隆 特任准教授/ロボットクリエイター
|
身の回りの機械製品の高機能化についていけなくなった、と感じたことはありませんか?
人とコミュニケーション出来るヒューマノイドロボットが、人間と機械の間を取り持ち、家電製品やホームセキュリティなどを人間に代わって操作してくれる。そんなロボットと暮らす近未来を、ロボットのデモンストレーションを交えながら紹介したいと思います。
|
|
| 15:00~15:50 |
「アジアの特性を生かした前立腺癌化学予防」 |
東京大学先端科学技術研究センター 赤座英之 特任教授/医学博士
|
欧米における前立腺癌の罹患率は、全男性のがん罹患率のトップであり、その予防に関する研究は急務となっています。また、日本を含むアジアでは、これまで欧米に比較して100分の1程度であった罹患率が急増していることが問題となっています。
したがって、罹患率のアジアと西欧の格差の要因を探ることは、西欧における罹患率の減少につながるだけでなく、アジアにおける急増を阻止することにもつながります。私たち研究グループが見出した、その重要な要因と対策についてご報告します。
|
|
| 会場: 生産技術研究所 An棟3階大会議室(An301.302) |
|
| 13:00~15:00 |
体験講演会 |
| 「高齢者転倒予防講座:転ばぬ先の足指トレーニング―新型バランス機器でトライ!―」 |
先端科学技術研究センター 田中敏明 特任教授
|
毎年数万人単位が転倒し、その多くが障害を負っている高齢化社会、日本。
健康作りとして転倒予防に関するバランス・歩行移動トレーニング方法をご紹介します。 また、ご希望の方には新型バランス機器も体験していただけます。
|
【お申込み】 参加対象:65歳以上の高齢者を中心に
往復ハガキ、FAX、メールのいずれかで、(1)住所、(2)氏名および年齢、(3)連絡先電話番号をご記入の上、「経営戦略企画室キャンパス公開担当」宛 お送りください。
〒153-8904 目黒区駒場4-6-1
東京大学先端科学技術研究センター
FAX:03-5452-5425
メール:communication@rcast.u-tokyo.ac.jp
(お問合せ 電話:03-5452-5424)
恐れ入りますが、応募多数の場合は抽選とさせていただきます。
|
|
| 会場: 生産技術研究所 As棟中セミナー室4(As311. 312) |
|
| 13:30~16:30 |
成果発表 |
| 「最先端研究を取り入れたジュニア科学者育成プログラム研究発表会」 |
「知の社会浸透」ユニット
『未来の科学者養成講座』(JST委託事業)を受講した高校生
|
東京大学生産技術研究所で実施している「最先端研究を取り入れたジュニア科学者育成プログラム」(JST 委託事業「未来の科学者養成講座」)の「最先端リサーチ体験プロジェクト」に参加した高校生が一堂に会し、数か月間にわたり東京大学に通い研究した成果を発表します。
|
オープニングセレモニー
研究室公開 研究テーマ一覧
理科教室 (要 お申込み)
未来の科学者のための駒場リサーチキャンパス公開 (中学生・高校生対象、要申込み)