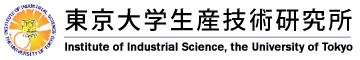|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
部門・センター毎一覧基礎系部門
機械・生体系部門
情報・エレクトロニクス系部門
物質・環境系部門
人間・社会系部門
大規模複雑システムマネジメント部門 大規模複雑システムは、必ずしも独立でない数多くのシステム入力のもと、線形のみならず非線形な様相を呈する莫大なシステム状態量、システム出力項目を有します。
高次協調モデリング客員部門
千葉実験所は千葉市稲毛区弥生町(本所発祥の地)にある本所の附属施設です。敷地面積は9.2ha,研究課題は所内にて公募されており,耐震実験設備や水槽施設を用いた大型実験研究や屋外観測,交通工学・車両工学,構造工学など広い敷地を必要とする研究,バイオ工学,加工成形等の実用化試験などが盛んに実施されています。施設の利用・管理のための管理運営委員会があり,須田実験所長以下6名の職員が保守・管理業務にあたっています。
マイクロナノメカトロニクスとは、機械、電子、光学、バイオ化学などの機能を持つ超小型の集積システムの研究です。最先端の研究の推進を第一の目的にして、①半導体技術、微細機械加工、バイオ技術を融合したマイクロナノ製造と集積化技術、②アクチュエータなどの基本素子、③光学、無線通信、バイオ医療、ナノテクへの応用に注力しています。また国際研究ネットワークの運営の中核を担っており、1995年に開始したフランス国立科学研究センター(CNRS)との共同研究(LIMMS)を発展させるとともに、これに6カ国を加えた国際研究グループ(NAMIS)を組織しました。年一度のワークショップや、大学院学生を集めた国際スクールを開催し、EU(欧州連合)プロジェクトなど多くの共同研究を実施中です。
本センターは、持続可能社会により近づくための方策を、材料の面から提案するために設立されました。産業的に重要な材料とその副産物について物質循環の検討、材料設計の境界条件の探査、材料生産プロセスの設計、さらには超長寿命材料や低環境負荷材料の開発などの先端研究を、国内外の研究機関と連携して行っています。
本センター(International Center for Urban Safety Engineering: ICUS)は、少子高齢人口減少、財政健全化、高度技術、低環境負荷、地方分権、縮小均衡などを特徴とする21世紀の我が国において、人々が豊かに安全に暮らす都市環境を実現し継続するための課題の抽出と解決策の提案を目的に設立されました。先進国はもちろん途上国においても将来確実に同様の課題を抱える状況の中で、課題先進国としての我が国が国際的に期待される役割でもあると考えています。研究分野として、(1)「災害安全社会実現学」、(2)「国土環境安全情報学」、(3)「成熟社会基盤適応学」を掲げ、「先端研究の推進」、「ネットワークの構築」、「情報の収集と配信」を通して、上記の目的を果たすべく国際的な活動を実施しています。
ナノ科学やナノ技術を駆使することにより、半導体量子構造、金属ナノ粒子、機能性分子などナノ量子構造中の電子、光子、スピンなどの量子状態の融合に向けた基礎研究を推進するとともに、それを基盤とする新たなエレクトロニクスの開拓と、イノベーションの創出を図ります。本所の物性物理、エレクトロニクス、材料科学の研究者が、既存の組織の枠を超えてダイナミックに集結し、学際的連携・産学連携のもとで光電子融合エレクトロニクスという研究分野を創出するとともに、新たな産業技術基盤の確立に貢献します。
本センターは、社会的要請の高い諸問題に対するソリューションの創出に向けて、人間の行動と社会活動の理解にもとづき実世界とIT基盤とを密に結合した情報システムに関する研究開発を推し進めています。特に、人の詳細な行動および社会活動のセンシングとモデリング、大規模データ解析、超高性能データエンジン、大規模センサネットワーク、情報セキュリティとプライバシー等の研究に取り組むとともに、それらの融合により、人間行動・社会活動の解析を軸に実世界とクラウドを一体として扱う技術の体系化に向けた活動を進めています。
2013年4月に新メンバーを加え、革新的シミュレーション研究センター(CISS)は改組しました。新CISSではHPCI戦略プログラム「分野4 次世代ものづくり」の代表戦略機関として引き続きプロジェクトを推進していくとともに、これまでに開発してきた実用的シミュレーションソフトウェアの普及活動を積極的に展開します。
本所と工学系研究科が共同で設立したエネルギー工学連携研究センターは、本学におけるエネルギー・環境技術に関する工学分野の国際的連携拠点の形成、エネルギーの高度有効利用技術の開発、エネルギー工学の学問体系構築、サステイナブルな産業・社会の構築を産官学連携により推進することを目的としています。広範に広がるエネルギー分野において、全体を俯瞰しつつ長期ビジョンのもと革新的なエネルギー・環境技術の開発を行い、エネルギーと環境問題の同時解決を目指します。
次世代モビリティ研究センター (ITSセンター) 本センターは、先進モビリティ研究センターで培った分野融合研究の成果をベースに、ITS(Intelligent Transportation Systems)技術の社会実装を目指し、地域ITSセンターと産官学による社会制度も対象とした研究体制を構築して、「自動運転」による次世代交通システムの研究とビッグデータ時代における総合的なモビリティ社会のデザインの研究の二つのテーマを中心に研究を進めます。研究開発と同時に地域実装や社会システム・制度の在り方などの検討にも取り組みます。
本所の強みであるデバイス技術・数理工学・生物工学・臨床医学を融合し、学内の分子細胞生物学研究所および医科学研究所並びに国立国際医療研究センター研究所などの専門研究機関との連携を深化させつつ、「細胞や組織等の生体材料を使ったものづくり」を体系化するとともに、細胞から個体、予防から診断に至るまでの革新的医療システムを創生、我が国の関連産業の発展に貢献することを目的とします。このために、前臨床段階まで工学者が深く関与する体制を構築し、工学者主導の国際的医療システム研究開発拠点を構築します。
半導体ナノテクノロジーを中核技術に、次世代情報・通信技術の基盤となるナノ光電子デバイス技術およびLSIフォトニクス融合技術の研究開発を推進し、その社会への展開を図ります。特に、産学の英知を集約した強い連携の下、ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構や先端科学技術研究センターなどとも密接に連携し、文部科学省および経済産業省のプロジェクトを中心に研究を推進しています。これにより、駒場リサーチキャンパスをナノエレクトロニクス研究の世界拠点のひとつにすることを目指しています。
バイオナノ融合プロセス連携研究センター 本センターは、異分野融合型次世代デバイスの研究を本所にて強力かつ円滑に実施するために、2008年7月に設置されました。
本センターでは、我が国独自の学問「数理工学(Mathematical Engineering)」やセンター長自身が構築したカオス、フラクタル、複雑ネットワークなどの工学応用を目指す「カオス工学(Chaos Engineering)」を基にして、複雑系数理モデル学の構築とその具体的な分野横断的な複雑系科学技術を開発しています。現在、内閣府最先端研究開発支援プログラム「複雑系数理モデル学の基礎理論構築とその分野横断的科学技術応用」プロジェクトによる研究を基盤としてさらなる発展を目指しています。
本センターは、産官学の連携により、ものづくりに関する先進的・革新的研究開発を進め、高付加価値生産、環境対応型生産ならびに省資源型生産に貢献します。高付加価値生産技術としては航空機の主要素材であるCFRPやチタン合金、アルミ・リチウム合金の高品位切削加工技術を、環境対応型生産技術としては切削油剤や電力消費を大幅に減少させたセミドライ加工技術を、省資源型生産技術としては、チタン切りくずリサイクルやレアメタルを大量に含む切削工具の寿命延長技術を研究対象としています。これらの研究開発を通じて、航空機製造に関する課題を解消するとともに、現代社会の持続的発展に向けた先進ものづくりを目指します。
海洋探査システム連携研究センター 本センターでは、海洋底の総合的理解のため、本所の優れた海洋底探査技術を基盤として、関連する学外連携機関と連携し、音響計測技術、電磁探査技術、化学計測技術などの計測技術の高度化と計測データの統合を図り、新しい海洋鉱物資源等の広域探査技術を開発します。さらに、開発した技術を組み込んだシステマチックな運用技術を構築します。また、開発技術の実用化と汎用化を推進するため、開発技術の民間企業等への技術移転を進め、探査技術の普及を図ることで海洋に新たな産業を創生し、海洋産業を活性化して社会に貢献します。
ソーシャルビッグデータICT連携研究センター 本所と、情報通信研究機構(NICT)、国立情報学研究所(NII)との間において2013年12月に締結した情報通信分野に関わる連携協力に関する協定書に基づき発足した連携研究センターです。ビッグデータの高度利活用による多様な社会課題解決を目標とし、人間行動解析、データ処理基盤、サイバーセキュリティ、高速・頑健言語処理、情報可視化等の研究開発を推進しています。
本所とフランス国立科学研究センター(CNRS)は1995年以来、MEMS技術に関する国際共同研究組織LIMMSを運営、2004年には、CNRSの正式な国際研究組織UMI(Unité Mixte Internationale)に昇格し、本所では国際連携研究センターとして認定されました。LIMMSではこれまでに開発したマイクロ/ナノテクノロジー分野における広範なノウハウをもとに、ナノテクノロジー新分野の開拓、バイオ応用マイクロシステムの研究、先端的集積化マイクロシステムの研究を行っています。2011年には、EUプロジェクト(EUJO-LIMMS)に採択され、我が国初の欧州委員会による国際共同研究ラボEUJO-LIMMSとして、国際共同研究を推進しています。
本学とマックス・プランク協会は、炎症のメカニズムと関連疾患に関する研究を統合的に推進することを目的とした研究センター“Max Planck-The University of Tokyo Center for Integrative Inflammology”を設置しました。これによって、本研究分野に関する相互の学術的連携や人材交流等を図ります。センターの研究活動を通じ、新しい疾患概念の樹立や治療法の確立を目指すことも重要な目的です。また、本学が推進している医工連携の更なる拡大・発展にも寄与するとともに、このような学際的研究分野を担う人材育成に広く貢献できると期待されます。
本部門は、最新の高効率利用技術の研究開発により、エネルギー消費量の削減、エネルギー源の分散、再生可能な自然エネルギーの活用を図っていくことを目的としています。また、その推進にあたっては単に理論上の最高効率を求めるだけでなく、経済性、信頼性も兼ね備え確実に実用化につながるよう検証を行い、真に国際競争力のある技術の確立を図ります。研究分野はIGCC、IGFCなどの石炭高度利用技術、CO2固定化、および新型風力発電、斬新な波力発電などの自然エネルギー利用技術、さらには漁船エンジンの電動化などを含んでいます。
非鉄金属資源循環工学寄付研究部門 社会の持続的な発展には、環境を保全しながらリサイクルを推進し、資源を循環させる必要があります。良質な天然資源が減少するとともに資源ナショナリズムが台頭する現在、レアメタルはもとより、ベースメタルについてもリサイクルを推進することが、我が国にとって重要です。本部門では、レアメタルを含む各種非鉄金属に関して、製錬技術を基に新たな環境調和型リサイクル技術を開発するとともに、若手人材の育成に力を入れています。
ニコンイメージングサイエンス寄付研究部門 本部門は、産業に直結する光学の教育を行うことにより産学の距離を縮め、次代の日本の光学産業においてリーダー的役割を果たす人材を育成することを直接の目的とします。特色あるプロフェッショナルな環境下でのレンズ設計実習を含む授業は本部門においても継続しています。
建物におけるエネルギー・デマンドの能動・包括制御技術社会連携研究部門 本部門は、次世代エネルギーシステムに関して、創エネルギー、自然エネルギー、未利用エネルギー、エネルギー融通、省エネルギー等を最適活用するための、新たなエネルギーシナジー構造を構築します。
モビリティ・フィールドサイエンス社会連携研究部門 本部門は、準静電界を応用したモビリティ通信、センシング、微細構造による準静電界制御技術、生体における感覚器官の微細構造と電界の研究とその応用を目的とします。人間の移動行動や活動をより豊かにするためには、人間行動に伴う生体情報や感性情報のセシング・モニタリング、情報提供や評価に関する技術を革新的に発展させていくことが望まれており、交通システムをはじめとする様々な応用が期待されるフィールドサイエンスとモビリティ社会への適用について研究開発を実施しています。
炎症・免疫制御学社会連携研究部門 本部門では、炎症・免疫系におけるシグナル伝達・遺伝子発現の制御機構を中心に研究を進めており、関連疾患との関わりについて解析を行っています。確固とした分子生物学を土台とし、新しい技術や考えを積極的に取り入れながら、免疫系・生体防御系という複雑系をどう理解するかという分野の先端的研究を目指しています。臨床医学とも深くかかわる分野であり、新しい予防・治療法に路を開くことも視野に入れながら研究しています。
|
|
駒場IIキャンパス : 〒153-8505 東京都目黒区駒場4-6-1 連絡先: 所内連絡先一覧へ
|
Copyright(c) Institute of Industrial Science, University of Tokyo
|
||
| 千葉実験所 : 〒263-0022 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-8 TEL : 043-251-8311(代表) |