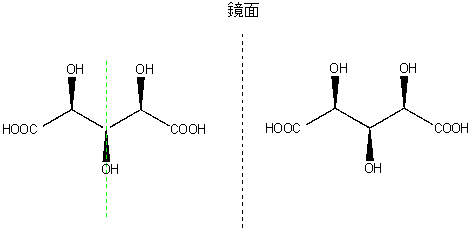有機1の立体化学の講義に関して
1.補遺・・・相対立体配置について
鎖状の有機化合物で主鎖をジグザグに書いたときに2つの置換基が「相対的に」同じ方向に出たものをsyn体,反対に出たものをanti体という。下の化合物で左の2つはsyn体,右の2つはanti体である。
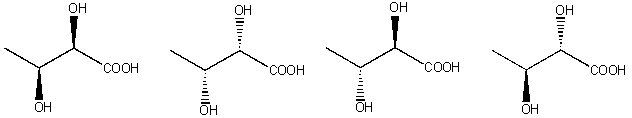
下の左の化合物はD-グルコースだが,これは,2,3-syn, 3,4-syn, 4,5-antiである。右はそのエナンチオマーであるL-グルコースだが,これも2,3-syn,
3,4-syn, 4,5-antiであることに変わりはない。
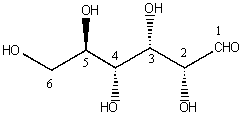
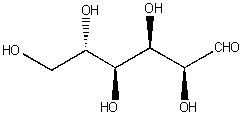
このように相対立体配置とは,各不斉炭素の立体配置がRなのかSなのかということではなくて,2つの不斉炭素の立体配置相互の関係のみを表すものである。
エリトロ/トレオは別の命名体系である。エリトロースと同じようにFischer式で描いたときに隣接した不斉炭素に結合した2つの置換基が同じ側に向いたものをエリトロ体,逆側のものをトレオ体という。この命名はよりマイナーであって,覚えなくとも差し支えない。
2.訂正
光学分割について:
『(R)-カルボン酸/(R)-アミンの塩を単離して”強塩基で処理すると”(R)-カルボン酸が得られる。』
は間違いで
『(R)-カルボン酸/(R)-アミンの塩を単離して”強酸で処理すると”(R)-カルボン酸が得られる。』
が正しい。
一般的に有機物の水への溶解度は低いが,塩になるとイオン性なので比較的よく溶ける。(R)-カルボン酸/(R)-アミンの塩を強酸で処理すると,強酸の(R)-アミン塩が水に溶け,(R)-カルボン酸が遊離してくる。
なお,カルボン酸を分け取ったあとの水溶液を今度は強塩基で処理すると(R)-アミンが遊離する。これを回収すれば,再度光学分割に用いることができる。このように,分割剤はリサイクル可能である。
3.質問の多かった事項
・メソ体がよくわからない。
(回答)2つ以上の不斉炭素をもち,かつその分子の鏡像がもとの分子と同一の立体配置をもつものをメソ体という。すべてのメソ体は光学不活性(旋光度が0°ということ)である。また,メソ体には「分子内に鏡面をもつ」という構造上の共通点がある。講義ではメソ体をFischer式で示したが,楔形表示で見ると下記のようになる。
meso-2,3-ブタンジオール
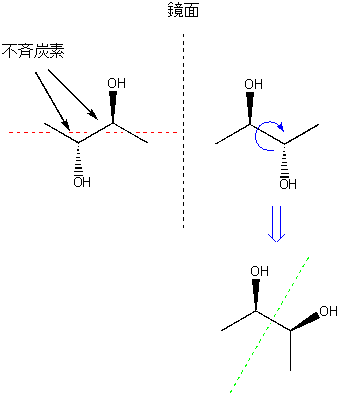
上段左の構造を赤点線を軸として180°回転させると上段右の構造となり,これらの分子同士が同一であることが分かる。また,上段右の構造の中央のC-C結合の周りに180°回転させると下段の構造になる。これは緑点線の部分が鏡面となる。『分子内に鏡面をもつ』とはこのことを意味している。
リバル酸
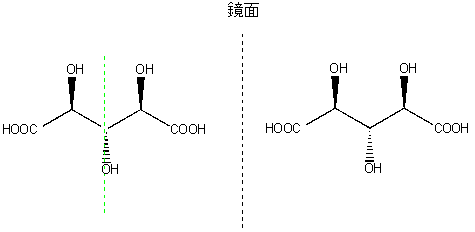
緑点線は分子内に存在する鏡面を表す。鏡像関係にある左右の分子が同一であることは誰の目にも明らかである。
キシラル酸