 電話交換室 橋浦 紀美子
電話交換室 橋浦 紀美子
 電話交換室 橋浦 紀美子
電話交換室 橋浦 紀美子「はい。東大生研でございます。」
「○○さん、外線からです。どうぞお話しください。」
優しい響きのこれらのフレーズを知らない人はいないだろう。生研の電話交換は現在4人で対応していて、そのリーダーがこの人、橋浦さんである。
ファックスや電子メールと違って電話は人と人が直接はなしをする道具である。橋浦さんは、その会話を人が取り継ぐという仕組みを愛し、この仕事に誇りを持っておられる。「私達の出番はほんの一瞬なんです。その短い言葉でも、相手の方がさわやかな気持になるような、そんな人間味が出るよう心掛けています。たとえ嫌なことがあっても、笑顔でいるよう努めています。未だに顔色が声にも出てしまいますので(笑)」35年目を迎えられたプロの言葉である。
このようなお仕事ゆえ、気分転換は不可欠。橋浦さんはスポーツ愛好家でもある。特にスキー歴は相当なもので、シーズンにはご家族と毎週のようにスキー場に通われるそうである。ご謙遜なさるものの、かなりの上級者とお見受けする。また、数年前からはテニスも楽しまれている。でも、ケガには十分お気を付け下さい。(A.S.)
 駒場II地区における新営計画の現況について
駒場II地区における新営計画の現況について所長 鈴木 基之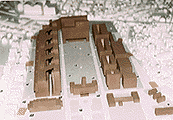
本所の駒場II地区における新営計画は、既にお知らせ致しておりますように平成7年度の補正予算で当面の整備計画の約1/6の面積の予算がついており、今後、第二期、第三期が継続的に進行していくことになりますので、この大事業を本所一丸となって理想的な形へ実現していくことが必要となります。本所においては、これまで建築計画調査室、研究推進室において各々研究スペース、研究設備の計画を検討して参りましたが、いよいよ新営が実行段階に入りますので、これまで各室で分担していた種々の業務、作業を一本化し、また関連情報の整理とスムーズな伝達を促進するために新営関連のヘッドクォーターを設置することと致しました。これを移転準備室(仮称)として、下記の方々 に参画をお願いいたしました。
移転準備室(仮称)メンバー
(室長)村上周三教授、(室員)西尾茂文教授、藤田博之教授、前田正文助教授、小長井一男助教授、藤井明教授、阿部経理課専門職員、竹内情報普及掛長、(専門委員) 曲渕邦英助教授、
今後、移転準備室において新営、再配置に関する作業を集中的に行っていきますが、状況に応じ準備室の下にタスクフォースチームをAdhocに作って進めていくことも必要になると思いますので宜しくご協力をお願致します。この室の作業状況が全所に詳らかになることを考え、専用の作業室を設け、必要な書類などを全てここで管理するように致します。なおキャンパス計画の策定に生研の意志を反映していくうえでのキャンパス特別委員会の使命と機能は従前どおりです。
また駒場Ⅱ地区における埋蔵文化財に関する調査によれば史跡等が存在するとの報告はなく、このため具体的な建築は建築仕様の公告、入札の手続きを経て今秋中に着工の見込みです。そのための基本計画案(写真2)の詰めに本部キャンパス計画室で鋭意努力されているところであります。駒場の現況(写真1)はこれまでの同キャンパスの歴史的な経緯(後述)を反映して、歴史的なあるいは老朽化した建物、未使用建物が入り交じりその再開発が必須の状況ですが、新たな基本計画案は中央に公開の広場を設けるなど地域住民の生活環境にも配慮したものになっております。駒場キャンパス開発の経緯
駒場IIキャンパスは1927年にそれまで農学部の敷地の一部であったものが本学付置の航空研究所の移転先として選定され、庁舎の建設が行われた。航空研究所は1946年勅令をもって廃止され、同年理工学研究所が11部門をもって設立された。理工学研究所は1957年まで継続し、1958年から我が国における航空研究の再開にともなって航空研究所(22部門)が再発足した。一方宇宙科学に関する研究は当時、本所(生産技術研究所)において精力的に進められており、学術会議の勧告に基づいて、1964年本所のロケット関係部門、新設の宇宙科学、宇宙工学部門とともに、航空研究所が発展的に解消して転換した部門を有する宇宙航空研究所が本学付置の全国国立大学共同利用研究所として設置されることとなった。研究部門は38であった。宇宙研究の拡大に伴い、1981年には宇宙科学研究所は本学を離れ、国立大学共同利用機関となり、その後主たる研究施設は相模原へ新設されることとなる。 その後、駒場地区には、1987年に学内共同利用研究施設として先端科学技術研究センター(4大部門、教授・助教授計33名)が設置された。また、1991年に本学に設置された気候システム 研究センター(教授・助教授計8名)、1992年に設置された人工物工学研究センター(3部門)が駒場に現在研究場所を置いている。 現在、駒場IIキャンパスは97,433m2の土地に国際交流会館、宿舎敷地などと共に、未使用建物も含み、老朽化した建物、歴史的な建物も建っており、今後キャンパス全体を再開発する総合的な計画が本学の将来の発展の為にも不可欠であることが合意されており、本所と先端科学技術研究センター、さらに本年本学に設置された国際産学共同研究センターが手を携えて次の世紀における本学の社会に開かれた科学技術の拠点を構築していくことが重要である。

 産業界諮問パネル会議成功裡に終わる
産業界諮問パネル会議成功裡に終わる

生産技術研究所では「研究所公開」に合わせて、6月5日、6日の二日間、我が国の産業界の主要分野のリーダー的な方々13名(別表)をパネルメンバーに迎え、産業界パネルによる第三者評価を行なった。これは、先年行なわれた5名の外国人著名学者による国際諮問パネルに続くもので、今後予定されている国内の学識経験者による学術諮問パネルと合わせ、多方面からの評価を頂く計画の一環である。
パネル座長の富士通(株)会長山本卓眞氏と副座長の(株)東芝常任顧問高柳誠一氏は、6月7日に記者会見を行い、評価結果の概要を報告された。産業人の視点から、本所の主として社会貢献に向けての活動と将来計画全般に対して、パネル会議での評価と的確な助言を述べられた。
日本の社会・経済の将来のため産業界と大学の連携が注目される折、今回の本所の試みは学内外からの関心を集めた。出張が予め決まっていたため総長、副総長の出席は頂けなかったが、初日夜の懇談会には、岡本工学系研究科長、文部省早田学術国際局研究機関課長、通産省林基礎産業局長、平石工業技術院長、学術振興会佐藤常務理事など多数の来賓が参加された。また、記者会見では各社の記者14名が参加し、活発な質疑が交わされた。
パネルメンバーは限られた時間を最大限に活用し、教官からのヒアリング、生研公開中の所内見学などからの情報を基に、2度にわたる総括会議で所長からの諮問事項に基づき本所への意見をまとめて頂いた。御多忙中を本研のために貴重な時間を割いて下さったことに厚く御礼申し上げたい。
ヒアリングに際しては、鈴木所長他、社会貢献や産業界との協調に特色のある研究センター、研究グループなどの代表の教官12名が説明に当たり、また運営に関しては15名以上の教官と事務官が諸行事の責任を分担した。第三者評価のための資料は305ページにも及ぶものであり、本所の教育研究活動の活発さが余すところ無く記されている。
本所では、8月末に受領予定の産業界パネルの正式報告を受けた上で、年内に本所の見解を含めた最終報告書を公表する予定である。
今回の産業界諮問パネル会議の成功は、まさに関係者全員の御協力の賜物であり、この機会を借りて心から感謝申し上げたい。
(第3者評価特別委員会座長 坂内 正夫)
(産業界諮問パネルWG座長 藤田 博之)記者会見での発表概要
第三者評価産業界諮問パネルに対する諮問事項は、以下の4項目であった。
・生産技術研究所の産学連携を含む社会貢献に関する評価。
・社会貢献の視点から特に推進すべき課題について。
・研究所の研究体制について。
・生産技術研究所と産業界との研究協力を更に発展させる方策について。
これに対する産業界パネルからの暫定報告の概略は次の通り。
生研は、産学の協力において我国で最も特徴のある研究所であり、その活動は評価できる。
特に評価できる点は、
1)理念として4つの貢献(知的貢献、社会貢献(産学協同を含む)、国際貢献、教育貢献)という4本柱が確立している。
2)基礎から応用までの幅広い分野で活発に研究活動を行っている。
3)異分野間での総合的な融合がうまくなされている。
4)研究推進室などにより研究マネジメントがスムーズであり、また内部における研究活動の相互チェック機能が保持されている、など。
一方、今後更に努力が期待される点は、1)世界をリードする工学技術を日本で創出することによる、国際社会、産業界への寄与へ向けて一層の努力をすること。
2)生産技術研究所の特長を生かした、複数分野の能力を持つなど時代が求める人材を育成すること。
3)新設された国際・産学共同研究センターを有効に活用して生研の特徴を生かした産学連携の強化をはかること。
4)幅広く社会・産業界の課題を取り入れた研究テーマを設定する機能を強化すること。
5)エネルギー問題、環境問題など企業の枠を超えた工学へさらに注力すること。
6)知的財産権の重視を行うこと。
など。
生産技術研究所としては、上記の暫定報告を受け入れて、生研の理念に基づく社会貢献、産学連携のあり方やその強化のための具体的方策について、更に踏み込んだ議論と実践を開始するつもりである。
(第3者評価特別委員会座長 坂内 正夫)
(産業界諮問パネルWG座長 藤田 博之)

 生研公開開催される
生研公開開催される
恒例の生研公開が6月6日・7日の2日間にわったて行われた。両日とも気温25度、快晴という好天に恵まれ、受付来所者は3,566名であった。一昨年が5,269名、昨年が4,072名であり、来所者数は減少傾向にある。これは世の中の景気と相関が有りや無しや。
初日には小林敏雄(第2部)、平川一彦(第3部)、山本良一(第4部)の各教官、2日目には尾島俊雄(第5部)、黒田和男(第1部)の各教官の講演が、いずれも第1・第2会議室で行われた。どの講演も解かりやすく話をされ、たいへん盛況であった。
また、初日の午前中には、第3者評価(産業界)のパネルメンバーの方々の見学もあったが、これにはもう少し時間があればという感もあったであろう。
研究室の展示は、ますます「電子化」してきた。インターネットで常時情報を公開している今日、物理的に扉を開ける「生研公開」では、板の上に書いたポスターや実験装置を眺めながら、担当者とじっくり話をする方が楽しい、という声もあるようだ。(A.S.)
 ハンガリー・ヴェスプレム大学工学部と学術交流協定を結ぶ
ハンガリー・ヴェスプレム大学工学部と学術交流協定を結ぶ本所13番目の交流協定を,今までのメモランダムを拡充する形でVeszprem大学工学部と結びました。生研の創立と同じ1949年に形をなした同大学は,工学部(化学工学・環境工学・環境管理・情報・電気・機械の6学科)と人文自然科学部(化学・数学・言語学・演劇学ほか)の2学部をもち,ブダペストの南西110キロ,バロック風の美しい町ヴェスプレムにあります。
調印式はマロニエやリラ,アカシアが今を盛りの5月15日,ヴェスプレム大学の小講堂で行われました。日本から鈴木所長ご夫妻・小職・小野国際交流専門職貝ほか3名,同大学からガアール工学部長,ホルヴァート副工学部長はか教官団に加えて多くの院生も列席し,まずは意表をつかれた両国国歌の演奏,協定書の朗読,協定書(マジャール語・日本語・英語)への署名,乾杯・・‥と厳粛な儀式のあと,以前ノーベル賞学者も登壇したという院生向けの特別講義(30分)を鈴木所長がやら(さ?)れ,真剣なお顔を久々に(?)拝見いたしました。(国際交流室長・渡辺 正)
 イブニングセミナー「地球と人間のための化学」
イブニングセミナー「地球と人間のための化学」平成8年度前半のイブニングセミナーは、4部が担当し、「地球と人間のための化学」という題目で毎週金曜日の夕方、8回にわたって行われた。新素材・エネルギー・水・化学物質・資源・地球環境の問題などについて、化学の視点から解説が行われた。本セミナーは教養学部の全学自由研究ゼミナールもかねて、広く一般から聴講者を募集して行われた。さいわい、多方面から多くの参加を得ることができた。アンケートによると「たいへんわかりやすかった」、「化学の大切さが認識できた」と好評であった。特にこれをきっかけに若い学生・参加者と生研教官との間に新しいコミュニケーションを築くことができた。(第4部 加藤 隆史)
 生研OB座談会「生研の生い立ち」
生研OB座談会「生研の生い立ち」去る4月27日(土)、関野克、一色貞文、鈴木弘、勝田高司の各名誉教授にお集まりいただきいて「生研の生い立ち」というテーマで座談会を開催した。これは、現在の生研が駒場移転をはじめ大きな節目を迎えるに当り、第二工学部から生研への移行、生研の麻布移転などについて、当時実際にご苦労をされた先生方から直接お話を伺おうというのが主旨である。
当日、午後3時に千葉実験所にお集まりいただき、ちょうど満開の八重桜の下で、森瑩子さん(本年4月定年退職)による野立てでお茶を楽しんでいただいた後、場所をホテルグリーンタワー幕張に移し、鈴木所長と橘(出版委員長)が参加して約2時間にわたってお話を伺った。第二工学部の成立から戦争直後の学内における立場、生研への移行の過程、千葉から麻布への移転の経緯等について、いろいろと生のお話を伺った。現在の恵まれた環境で研究をさせていただいている我々としてきわめて感銘深いものであった。詳細は9月発行の「生産研究」に掲載予定であるので、乞御期待。(橘 秀樹)

 5月28・29日
5月28・29日平成8年度新規採用者研修および新任教官等研修左:本所においての研修風景
右:駒場キャンパス見学
下:千葉実験所見学
 6月20日
6月20日構内環境整備の実施
 新任のご挨拶
新任のご挨拶第一部 客員部門 助教授 加藤純一
無事,国会予算も通過いたしまして,5月11日付で高度協調モデリング客員部門・助教授として着任いたしました。本務は,理化学研究所・光工学研究室において光応用計測の研究にたずさわっております。本部門の本質的な意味の理解は未だできておりませんが,東大・生産技術研究所という歴史のある組織の雰囲気を満喫するとともに,この機会を最大限活かした研究活動を行いたいと思っています。基本的には,非線型光デバイスの時空間領域での新しい応用を目指したいと思っています。趣味は,テニス・計算機いじめ,および海・山への旅行です。良い機会がありましたら是非お誘い下さい。
 昇任のご挨拶
昇任のご挨拶東京大学国際・産学共同研究センター 教授 藤森照信
このたび、教授に昇任いたしました。正確にいうと、駒場に新設された国際・産学共同センタ-の教授となり、生研の方は、兼担教授となります。兼担教授の生研での任務については、研究室運営はスタッフ、大学院生、予算を含めこれまで通り、教授総会、各種委員会の任務も変わらないことになりそうです。
国際・産学の設立目的は、ナカグロが付いていることから分かりますように、国際か、産業かどちらか(もちろん両方でも)尽力することですが、私の場合、現在、アジア各国の大学と歴史的な都市と建築についての共同研究を続行中であり、この方面をさらに発展させるつもりですので、これまでどうりよろしくお願い申しあげます。
 転任のご挨拶
転任のご挨拶第4部 助教授 加藤隆史
7月1日付で工学系研究科化学生命工学専攻に移りました。院生として、また教官として、合計約10年間生研にお世話になりました。特に、教官として着任してからは総合工学研究所としての生研の“文化”というものを十分に楽しませていただきました。いろいろな方とお会いすることができました。感謝いたしております。液晶などの機能材料・自己組織材料を分子レベルの視点から研究していますが、生研のような、多種多様なものが有効に協調して働く材料も今後、新しい機能システムとして創っていきたいと考えております。今後ともよろしくお願いいたします。

 受賞
受賞
- 第2部 教授 中川 威雄{鶴 英明(本田技研)・稲葉 善治(ファナック(株))}
1996.5.21
粉体粉末冶金協会研究進歩賞 社)粉体粉末冶金協会
電動式CNCプレスによる粉末成形の研究- 助手 村田泰彦 助教授 横井秀俊
1996.1.31
プラスチック成形加工学会 平成7年度論文賞 (社)プラスチック成形加工学会
ガラスインサート金型による繊維配向課程の可視化解析(第2報)繊維追跡撮影装置による解析

将来を見すえた計画が重要であることは疑いない。しかし将来を見すえることはなかなかにむずかしい。今、生命進化論を工学に応用することがさかんである。進化論的研究計画哲学を考えてみた。
「創造は模倣から生まれる」ということばがある。模倣ということばが悪いイメ-ジをもつため誤解される表現ではあるが含蓄にとんだことばである。これは生命進化が膨大な世代間で正確な遺伝子コピ-をくりかえすなかで、個体における遺伝子コピ-のわずかな失敗とそのミスコピ-の種全体への拡散が進化(創造)の源となってきたという感慨から生まれたことばである。人間の文化・技術の発展もこの生命進化になぞらえられる。人間は先例にならって生活する。先祖が生存してきた状況を再現することが、もっとも確実な自分の生存保証となる。なにごとも正確に模倣することはむずかしい。先祖の模倣の過程で、だれかが小さなミスを犯し新たな発見・発明となって集団のなかに拡散し文明が発展していく。この小さな発見、発明は、遺伝子の小さなミスコピ-にもたとえられるものでその時代文化背景に対しわずかな変化でしかない。魚類から突然人類が発生するわけもなく、中世の暗黒時代に、近代の電磁気学が突然生まれる道理もない。我々のできることは、現状の生活・文化の模倣のなかから数多くのちょっとしたミスコピ-を生成させ、世間に拡散させることである。独創的研究は模倣の奨励とミスコピ-の生成を許容する姿勢から生まれる。ミスコピ-を許さない世界に進化はない。誤解されると困るのでひとこと付け加える。他分野の模倣にはミスコピ-が生じやすい。おなじ分野の模倣は正確に行い得るがミスコピ-も生じない!。
「利己的な遺伝子」はド-キンスさんのベストセラ-であるが、このことばにも悪いイメ-ジを逆手にとった進化論的哲学がある。ミスコピ-として生成した遺伝子にそもそも良い、悪いがあるはずがない。悪い遺伝子は淘汰され良い遺伝子が残されるなどと考えるのは、お人好しの人間の思い込みである。遺伝子の任務は、子孫に遺伝子情報を伝達し、種の間に拡散させることである。これを上手に行ったミスコピ-遺伝子が結果として今、存在している。生命体に有利と思われるミスコピ-遺伝子でも、効率的に種の間に拡散し子孫に伝達されなければ絶滅してしまう。「利己的な遺伝子」のかわりに「生研の重点研究}とおきかえて,いろいろシュミレーションするとおもしろい。科学技術の研究計画にこの進化論的哲学をどのように導入するかは、意見のわかれるところであろう。
厳しい競争にさらされるウオ-ル街のビジネスマンの間でド-キンスさんのこの本がよく読まれたそうである。模倣により同じ事をしているだけでは競争に生き残れない。そうしたビジネスマンにこの進化論哲学がどのような感慨を与えたのか知りたいものである。(第5部 加藤信介)

 第5回技術発表会
第5回技術発表会技術系職員を中心に第5回の技術発表会を開催します。様々な技術的話題に関する講演発表が行なわれ、終了後には懇親会も予定されています。多くの方のご来場をお待ちします。開催日時:平成8年9月26日(木) 午前9時30分~午後5時
場所:生産技術研究所 第一、第二会議室
問合せ先:小久保 旭 実行委員長(内線2142)
 第4回 平成8年度東京大学教室系技術職員研修(械械工作関係)の実施について
第4回 平成8年度東京大学教室系技術職員研修(械械工作関係)の実施について前年度に引き続き、今回で第4回目となりますが、たいへん好評なので今年度も教室系技術職貝を対象に下記の通り行われます。皆様のご協力をお願いします。目的: 実験的研究に必安な機械設計・加工技術の専門的知識及び基本的技術の修得。
開催日時:平成8年10月1日(火)~4日(金) 4日間
場所:生産技術研究所 試作工場
 生研セミナー開講
生研セミナー開講生産技術研究所の教官が中心となり、それぞれの研究分野の基礎知識や最新情報を懇切丁寧に講義いたします。本年度のスケジュールは下記のとおりです。講義概要、時間割、受講料、申し込み方法は、生産技術研究奨励会(Tel.Faxとも03-3402-1331)までお問い合わせ下さい。平成8年度 生研セミナー場所 東京大学生産技術研究所 207コース 最新超精密研削技術一電気泳動現象を利用した研削技術一 講師 谷 泰弘 助教授 外3名 1996年10月8 日(火) 定員 40 名 受講料 6,000円 / 12,000円 208コース 射出成型現象の可視化実験解析(第6回)一金型内現象編一 講師 横井 秀俊 助教授 外1名 1996年10月23(水)(六本木)、24日(木)(千葉実験所) 定員 30 名 受講料 12,000円 / 24,000円 209コース 射出成型現象の可視化実験解析(第7回)一加熱シリンダ内現象編一 講師 横井 秀俊 助教授 1996年10月25(金)(千葉実験所) 定員 30 名 受講料 6,000円 / 12,000円 210コース 結像光学系の基礎 講師 黒田 和男 教授 1997年1月24日(金) 定員 20 名 受講料 6,000円 / 12,000円
 生研基礎講座
生研基礎講座金属素材の創形創質加工- 理論と応用 -
講師 教授 木内 学第1回 基礎理論と解析手法 10月22日(火)・23日(水) 第2回 板材の製造技術とその矯正技術、成形技術 11月12日(火)・13日(水) 第3回 管材の製造技術とその二次加工技術 12月10日(火)・11日(水) 第4回 棒・線・形材の製造技術 1月20日(月)・21日(火) 受講料:生産技術研究奨励会賛助員の方 48,000円/ 一般の方 96,000円 なお、お申込みと同時に入会された場合は賛助員扱いとなります。 生研基礎講座、生研セミナーは、生産技術研究奨励会が主催しております。上記に関するお問い合わせは:東京大学生産技術研究所 (財)生産技術研究奨励会 TEL/FAX 03-3402-1331 e-mail:fpis@interlink.or.jp
 生研イブニングセミナー 「都市の形とダイナミックス」
生研イブニングセミナー 「都市の形とダイナミックス」人々の営みや社会の構造の変化を敏感に反映してさまざまに形を変える都市。
情報ネットワークの飛躍的な拡大や交通のインテリジェント化から、大規模な地震などに対する安全性の一層の向上、環境問題への対応など、都市を変革しようとする力はこれからもますます大きくなります。
しかし、その一方で都市は、変化を積み重ねてきたストックとしての顔、歴史をはぐくんできた顔も持っています。
都市の形やダイナミックスを構成するさまざまな要素、情報、環境、安全、水、歴史などを切り口に、これからの都市のあり方について、全9回のオムニバス形式でセミナーを開催いたします。
参加費は無料です。どなたでも是非ご参加下さい。日時:平成8年10月11日(金)から12月13日(金) (毎週金曜日 午後6時から7時30分まで) 場所:東京大学生産技術研究所 第1会議室(正面玄関真上、3階) 講師と演題(予定): 藤森照信 教授 風水の正体 10月 11日 加藤信介 助教授 都市の北風と太陽 10月 18日 虫明功臣 教授 都市と水環境 10月 25日 桑原雅夫 助教授 都市のモビリティ 11月 1日 大井謙一 助教授 都市の補強 11月 8日 古関潤一 助教授 都市の足元 11月 15日 曲渕英邦 助教授 都市と意識 11月 22日 片山恒雄 教授 都市の安全 12月 6日 村井俊治 教授 都市と情報 12月 13日 参加費と参加方法: 参加費は無料です。事前の参加申し込みも必要ありません。

 バーゼル大学にて
バーゼル大学にて第2部 教授 川勝 英樹
現在、フランスとスイスの国境近くのモンベリアールという小さな城下町に住んでい ます。ここはジュラ紀で有名なジュラ山地の北の端にあたり、十六、十七世紀にはドイツルネッサンスの中心地として栄えたところだと云われています。周囲にはローマ遺跡が点在しており、過去が短く感じられます。現地にはフランス科学研究庁の走査型顕微鏡の研究室がある上、車で小一時間のところには同研究庁の振動子物理計量研究所や、顕微鏡の分野で有名なスイス、バーゼル大学があります。研究面で極めて恵 まれた場所といえます。
さて、私は走査型顕微鏡から派生したともいえるサブミクロンの機械振動子の研究をしています。振動子が極めて小さいため、飛躍的な力の検出分解能の向上が期待できます。このテーマは新しいため、いろいろな方法での実現の可能性があり、やり甲斐があります。が、一方では落とし穴も多く、近い分野の研究者との交流が役立ちます。写真はフランスの新聞から切り抜いたもので、記事は、よくあるように”日出づる国より研究者来る”の文句ではじまるものでした。モンベリアールでは有史以来の日本人ということで、唯一、珍しい、ということで掲載となりました。
久しぶりに記事を引っぱり出してながめていると、成果の記事もないと締まらないな、などと欲張りにも思っております。最後に紙面をお借りして生研や専攻の先生方、事務部の方々、留守を守ってくれている研究室メンバーにこの渡航を御礼申し上げます。

 インテリジェント・スペース、ロボット・ネットワーク・システムの研究
インテリジェント・スペース、ロボット・ネットワーク・システムの研究第3部 橋本 秀紀
情報インフラストラクチャが華やかに議論され、高度情報化社会に向けて様々な取り組みが進められています。しかし、画像・音声を中心としたビット情報のみを取り扱うシステムの延長線上に、何か私達の生活を真に楽しく快適にするものがあるでしょうか?これが私共の問題意識です。
ビット(ディジタル化された情報)はコンピュータで大変取り扱いやすく、しかも結果が早く出るものです。コンピュータ・グラフィックスはその最たるもので、何の物理法則にも捕らわれずディジタル化された画像情報(ビット)は如何ようにも加工され、男の人の顔が連続的に女の人の顔にまでなってしまいます。一方、私たちが住んでいるこの物理世界はビットの世界(情報世界)と異なり大変取り扱いにくいものです。物をひとつ動かすだけでも、エネルギーを消費し動かす為の力を生成しなければならず大変めんどうなものです。
私どもは現在ディジタル革命として大きく進展しつつある情報世界と私達の日常空間である物理世界との接点に注目し、そのインターフェースが私達の生活に本質的な影響を与えるものと考え、ロボティクス・メカトロニクス技術を用いて賢いインタフェースに関する研究を行っています。
具体的には図1に示す「インテリジェント・スペース」の構築を目指しています。人間の感覚・機能をロボットや人工現実感を用いて拡大・延長し離れた所での共同作業等を実現しようと要素技術の研究を積極的に進めています。例えば図2のセンサ・グローブ2号機は人間の持つスキルの計測、コンピュータへの入力装置として開発され、計20個のアクチュエータにより力感覚を生成することができます。図3のロボット・ヘッドは7自由度を有し人間を認識し追跡する機能を有しています。また、六本木とロスアンジェルス間での遠隔握手装置も開発し通信実験に成功しています。
この「インテリジェント・スペース」の先に私共は図4に示す「ロボット・ネットワーク・システム」を考えています。各ロボットが情報インフラストラクチャで結ばれ私達の社会を物理的に支援するものです。このネットワークこそが、3K作業、労働力不足、高齢化社会、環境問題といった私達の日常空間での問題を解決するものと確信しています。上左:図1 インテリジェント・スペース 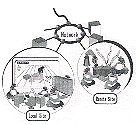
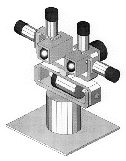
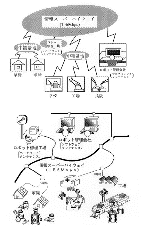
上右:図2 センサ・グローブ2号機
下左:図3 ロボット・ヘッド
下右:図4 ロボット・ネットワーク・システム