編集・発行 生研ニュース部会
INFORMATION
PLAZA
FRONTIER
写真は研究協力のお三方、左から水津知成さん、武原稔子さん、斉藤友美さんである。研究協力の主なお仕事は、科研費、受託研究費、奨学寄付金、その他民間等との共同研究費などの研究費の受入業務である。ここ数年は、文部省、科技庁、通産省など各省庁が行っている出資金事業によるお金が急激に増えており、それに従って仕事量が急激に増えているとのこと。また文部省以外からのお金の場合、受入手続きのルールが違ったりしていて、それのすり合せにご苦労が多いそうである。その他にも研究助成の公募をホームページに載せる作業、特許関係の事務など多岐に亘る仕事をこなしておられる。仕事の分担は水津さんが主に科研費の業務、斉藤さんが主に研究助成公募のホームページへの入力、受入資料作り、武原さんが外部との交渉その他を担当している。武原さんは本務以外にもセクハラ相談窓口の相談員でもあるのでお悩みの方はお気軽にお声を。また武原さんは、生研ニュースの創刊に尽力した初代編集室のメンバーである。第1号の岡田元所長から数えて60番めのご登場だが、当時は自分が表紙を飾ることなど考えてなかったのでは。
今後のお三方のさらなるご活躍を期待いたします。
(枝川圭一)
自動車のエンジンの中や室内エアコンなど、いたるところに見られる<乱流>は、名の通り乱れており、それを工学的に把握するのは易しくない。生研は、このテーマにグループを作って取り組んできたが、今回、谷口伸行助教授が公開発表したのは、乱流のシミュレーションを、専門家ではない技術者や研究者が活用できるようにしたフリーソフトウェアである。
記者からは、”既存のソフトとの差”、”世界で同種の研究グループはいくつくらいか”、”こういうソフト公開は多いのか”、”ユーザーは具体的にどういう場面で使うのか”などの質問があった。
谷口助教授は、”これまで、乱流は難しいと避けてきた人々が、これをツールとして基礎的なシミュレーションを試みるようになってくれば、工学発展への影響は大変に大きい”と協調した。
記者の顔ぶれは、各社少しづつローテーションしているようだが、生研記者会見の認知度はしだいに高まっているようである。
(第5部 藤森照信)
恒例の弥生会親睦レクリエーション大会が、6月14日から7月9日にかけて将棋、卓球、テニスの順で行われた。表に示すようにすべての種目で2位以上の成績をおさめた第1部が、一昨年、昨年に引き続いて3年連続で総合優勝にかがやいた。
○総合成績順位
チーム 得点 優勝 1部 13点 2位 4部 10点 3位 3部 9点 4位 2部 7点 5位 共通 5点 6位 事務 4点 7位 5部 3点
○種目別順位
種目 優勝 2位 3位 将棋 3部 1部 4部 卓球 1部 2部 3部 テニス 4部 1部 共通
(第1部 枝川圭一)

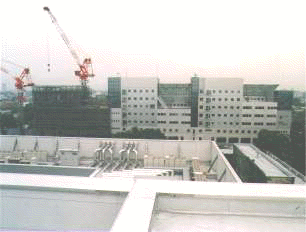
今秋に予定されている第II期研究棟(B棟)への引越しに向けて、いよいよB棟の準備も最終段階を迎え、什器備品等の設置やLAN・コンセント・電話などのインフラの整備が順調に進められております.また、第III期およびに第IV期工事となるD,E,F棟につきましても、来年度中の完成・移転を目指し、急ピッチに工事が進められている状況です.特に、前号の生研ニュース発行の段階では鉄骨組上げが終了し、各階床のコンクリートの打設作業が進められていたD棟ですが、既に上階までコンクリート打設作業も終了しその全容をあらわしております。またE、F棟につきましても、建物の基礎となる地下部分のコンクリート打ちが早くも終了する段階を迎えており、1階部分の鉄骨組上げが開始されております。これらの研究棟の建設作業に加え、駒場新キャンパス全体としての整備も着々と進められております.正門近く東側エリアの駐車場に関しましても、近い内にその半分程が利用可能となる予定です.B棟側に位置する東通用口につきましても、既に8月上旬に利用可能となっており、キャンパスへのアクセスがより一層便利になりました。
このように各研究棟工事、外構設備の整備が滞り無く進められていくに伴い、駒場新キャンパスにおける生研の活動がより一層活発化されていくわけですが、事務処理機構や保守管理体制といった具体的な組織の運営に関する部分を如何に整備していくか、更にはキャンパス周辺の近隣住民の方々にご迷惑をかけない利用を如何に心がけていくか、といった点も今後益々重要になって来ることと思われます。今後この面での一層の充実を図るとともに皆様のご理解ご協力を頂きたくお願い申し上げます。

第3部藤田博之教授を日本側研究責任者として、日仏初の共同研究ラボラトリーであるLIMMS(Laboratory for Integrated Micro-Mechatronic Systems, 集積化マイクロメカトロニックシステムラボラトリー)が創設されて今年で5年目を迎えた。
ヨーロッパ随一の研究機関であるフランス国立科学研究センター(以下CNRS)は、理工学系から人文系まで8部門で幅広く研究活動を行っている。その工学部門が1993年、当時micro/electro/mechatronics systemsの分野で一足先に成果を上げていた日本において共同研究パートナーを求めていた。そこで白羽の矢を立てたのが東大生研である。翌年にはパリで協定が締結されLIMMS発足の運びとなった。
LIMMSに在籍する常時12〜13人のフランス人研究者らは、研究テーマにより6つの受け入れラボに分散し研究活動を行っている。これはCNRS側だけで被包するのを避け、各ラボ内で情報交換をスムーズに行い、各自が日本の研究手法を学べるよう意識してのことでもあった。
日出る国のフランス人たち。未開の地に降り立ったかのごとく心細げな様子でLIMMSにやって来る彼らが、任期を終える頃には、箸を巧みに操り、寿司に舌鼓をうち、富士山の稜線、桜の美しさを愛でる事を知って帰って行く。「ここの独自の文化が好きなんだ」と皆が口をそろえる。「オリジナリティ」に敏感かも知れない。常に嗅覚をきかせ、雑多な中からそれをかぎ分けている。
ヨーロッパのメルティングポット、フランス。そこは、個人・個性・その自由を尊ぶ国でもある。だからこそか、彼らの持ち味は、強烈な個性と絶対の自信、そして自己主張。個性を尊重するか、尊重されるべき個性に乏しいと個として認めない、そんな厳しさも持っている。画一均質マクドナルド文化に浸かっていると、時に東洋の「ものさし」を差し出してくれるのは彼らであったりする。
日本とフランスという二つの個性。ぶつかり合ってストレスも生じよう。が、マイナスに働くかと言えばそうでもない。違うものをもった人々がボールを投げ合えばいいのではないか。この5年間で既に26人のフランス人研究者がLIMMSに所属し、共同の論文も96を数えた。個々のプロジェクトが完結し帰国したあとも、科学者としての知識に、彼らの日出る国での経験を加え、オリジナリティあふれる新しい何かを、彼の地で育ててくれているものと信じている。
(LIMMS 平野 ゆみ)
教職員
第3部 教授 石井 勝
受賞日:1999.7.14
受賞名[団体名]:1999 PES(Power Engineering Society) Working Group Award
IEEE Power Engineering Society[米国電気電子学会電力工学部門]
受賞項目:IEEE Std.1243「送電線の耐雷性 向上のためのガイド」
("IEEE Guide for Improving the Lightning Performance of Transmission Lines")
第5部 教授 加藤信介
受賞日:1999.8.9
受賞名[団体名]:Recognition and Certification of Being Elected
an Active Member of this Academy (室内空気科学国際アカデミー賞)
[The International Academy of Indoor Air Sciences
(室内空気科学国際学会)]
受賞項目:Contribution to Indoor Air Sciences
ミクロからマクロまで工学の対象となる様々な物の性質と構造についてわかりやすく解説いたします。予備知識は必要ありませんのでお気軽にお越し下さい。なお、講演の内容は都合により変更になることがあります。ご了承下さい。
| 開催日 | 講師 | 演題 | ||
| 10/8 | 教 授 高木堅志郎 | タイタニック −その神秘性と科学性− | ||
| 10/15 | 教 授 田中 肇 | ソフトマテリアルの世界 | ||
| 10/22 | 教 授 岡野 達雄 | 真空を極める | ||
| 10/29 | 教 授 寺倉 清之 | 量子シミュレーションが明かすミクロの世界 | ||
| 11/5 | 助教授 枝川 圭一 | 固体の原子配列と物性 −結晶、準結晶、アモルファス | ||
| 11/12 | 教 授 渡邊 勝彦 | 強さと寿命 −何故壊れるか− | ||
| 11/19 | 助教授 吉川 暢宏 | 形と強さ | ||
| 11/26 | 助教授 畔上 秀幸 | 物体や流れ場の形を最適に決める | ||
| 12/3 | 助教授 中埜 良昭 | 地震被害と建物の性能 −地震災害の軽減を考える− | ||
| 12/10 | 助教授 半場 藤弘 | 乱流 −乱れの中の秩序− | ||
今年も、技術系職員を中心に「技術発表会」を開催します。この発表会は、技術職員の知識および能力の向上を図り、お互いの技術交流、情報交換の場として続けられ、今年で8回目を数えます。多くの皆様に来て頂けるよう、お待ちしています。技術官以外の方々の参加も大歓迎です。是非一度、聞きにいらして下さい。
日 時: 10月28日(木) 午前10時〜午後5時
場 所: 本所第1・2会議室
問い合わせ: 技術発表会実行委員会 担当:小池
(E-mail: masahiro@hydro.iis.u-tokyo.ac.jp)
なお、発表会終了後に懇親会を予定しています。
講 師: 生産技術研究所・教授 木内 学
時 間: 午前10時〜午後4時20分
受講定員: 25名
開 催 日: 10月13日(水)、14日(木)
11月11日(木)、12日(金)
12月 7日(火)、 8日(水)
1月20日(木)、 21日(金)
受 講 料: 生産技術研究奨励会の賛助員の方
48,000円
一般の方 96,000円
なお、お申込みと同時に入会された場合は賛助員扱いとなります。
申 込 先: 〒106-8558 東京都港区六本木7-22-1
(財)生産技術研究奨励会 生研基礎講座係宛
FAX 03-3402-6372
問い合わせ先:受講に関するお問い合わせは上記FAX宛お願いいたします。
申込締め切り:開催日の1週間前とします。
主 催:(財)生産技術研究奨励会
協 力:東京大学生産技術研究所
第3部 講師 年吉 洋
計測技術開発センター 加藤(信)研究室
日本人の平均寿命は世界の最高水準に達している。世界の国々で平均寿命に大きな差異がある現実を直視するとき、異論はあろうが平均寿命が国家の一つの総合成績を示していると感じざるを得ない。高等教育の普及、良好な治安、災害防止施策による安全性の向上、所得の向上、上下水道やゴミ処理施設などの都市衛生設備の充実、感染症対策や予防医学の充実、疾病対策医療の向上など、様々な成果がこの寿命向上に寄与している。平均寿命は、国や地域の社会的基盤、組織、運営、ひいてはそこで暮らす人々の健康度を表すひとつのバロメターとも言える。
上記の様々な要素が平均寿命の向上にどのように寄与するかを分析することは、社会的にも政治的にも興味の深いところである。平均寿命が既に世界の最高水準にまで達し相応に国や地域の整備がなされた日本において、地域や年度の差異における平均寿命の差異は、医療の充実度も然ることながら、むしろ住宅の充実度や社会基盤の整備状況が大きな寄与を為しているとも言われている。人々の健康度に及ぼす住宅や社会基盤の充実度、これを支える地域の活性化の効果は深く大きい。
平均寿命はその地域の健康度を良く表す指標ではあるが、人々の健康度がこの平均寿命のみで計られるわけではないことは無論である。日本では、平均寿命は高くとも社会における個人のストレスが高く、結果として青少年や中高年の自殺率が世界でも有数の高いレベルに留まっている。さらには水や食料、大気や室内空気中の微量な化学物質による汚染の危険も根強く報告されている。これら微量化学物質の人体健康影響の医学的、疫学的検討、更に汚染物質の発生、輸送、摂取の性状把握や対策は必ずしも十分でなく不明な点も多い。我々はこれら人々の健康を脅かす要因を確認しその影響を明らかにする必要がある。工学特に我々の生活基盤を支える建築学、社会基盤学はこれらの問題に深く関わっており、その解決に果たす潜在力は極めて大きい。
地球の有限性が認識されて、その対応としてサステナブルな社会への移行が求められている。同じ地球上の他者や未来の住民である我々の子孫の健康度を脅かして、自身の健康度を向上させることは許されない。速やかに、サステナブルに、住宅や社会基盤の充実を図る方策を開発し、それを実施することが求められている。そのため、人々の健康度の高く、サステナブルである「健康な都市」の将来像を明らかにし、その道程を明らかにする研究が今強く求められている。
生研ニュースの創刊は1990年1月であり、ほぼ10年が経過して本号で第60号となった。今回IIS TODAYにご登場いただいた研究協力の武原さんがたまたま創刊当時の編集室のメンバーだったので取材の過程で創刊当時のお話も色々うかがった。当時、人の顔が表紙にでかでかと載った生研ニュースはとても斬新で、このような出版物を創刊することは一種の冒険であったようだが、今では生研構成員の「顔がみえる」ようなメディアとして確固たる支持をいただいている。途中、細かい変更はあったものの、基本的な紙面構成は当時のままである。ただ、60号ともなるとコーナーによっては記事が集まり難くなっており、生研ニュースの新たな展開に向けての議論をニュース部会で重ねているところである。
(枝川 圭一)