編集・発行 生研ニュース部会
INFORMATION
PLAZA
FRONTIER
写真は第2部吉識研究室の高間信行技術官。東京夢の島にあるマリーナでのスナップである。高間さんは、障害を持つ方々に広くヨットを楽しんで頂くことを目的としたボランティア団体ヨットエイドジャパン(YAJ)の中心的メンバーの一人であり、障害者用ヨットの開発に加え、定期的に行われる練習会にもサブコーチとして参加されている。残念ながら、障害を持つ方々のためのヨットの開発という面において我が国は遅れを取っており、現段階では外国から船体を購入しなければならないという。高間さんは、一日も早く日本から障害者向けヨット技術を海外に発信できるようにしたいと、厚生省プロジェクト「日本の海に合った障害者用ヨットの開発」の委員長として障害者の方々の声をもとにヨットの開発を進めてこられた。特に、縮小模型による性能検証試験などは千葉実験所の海流水槽を利用して行われたそうである。こうして、高間さんを始め1000人を超えるYAJのボランティアメンバーに支えられ、パラリンピックアトランタ大会では日本チームが初参加を果たした。結果こそこれからというものであったが、大きな一歩となったに違いない。現在は、2000年に行われるパラリンピックシドニー大会に照準を合わせその準備を進めているとのこと。最後に、高間さんが「自分がいかにして社会に貢献できるかということを考えた場合、研究者としての役割に留まらずYAJやSNG(Scientists for the Next Generationにおける活動を積極的に進めてきたいと思う」と熱意をもって語られるその姿が大変印象的であった。(佐藤洋一)
今回の定例記者発表は3月10日、第2部川勝英樹助教授、第3部年吉洋講師により行われた。
テーマは、<小さな振動子で原子を量る>である。 微少な質量をどう計測するかというテーマは、マイクロマシンなど精密化、極微細化が進む現代工学には不可欠だが、両先生は、モノサシとして使う振動子の超小型化に挑み、これまで10~1000ミクロンの長さであったものを100ナノメートルまで小さくした。言ってみれば、モノサシの目盛りを飛躍的に細かく刻むことに道を開いたのである。
記者からの質問の中心の一つは、どうやってそんなナノメーオーダーの振動子を作ることができるのかについてで、これには分かりやすい図解が用意されており、サンドイッチ状に形成した各種物質層を薬剤でエッチング(洗い落とし)し、分子レべルの細いカンチレバーと針を作る方法が示された。すでに試みた作成例も写真で見せられ、説明の理屈どうりに実現した振動子の姿に一同は感銘を受けたのだった。
(第5部 藤森照信)
3月20日(土)に第1・2会議室において、「Scientists for the Next Generation シンポジウム-科学教育における大学・研究所の役割-」が開催された。有馬朗人文部大臣・科学技術庁長官が「理科教育をどうするか」と題して基調講演を行った。その後、「科学教育における大学・研究所の役割」をテーマに文部省、通産省の各省庁関係者、高校の理科の先生および大学・研究所の関係者ら合計6人によってパネルディスカッションが行われた。
悪天候にもかかわらず、小中高校の理科・数学の先生および大学・研究所の先生をはじめ約150名ほどの参加があった。また、東京近郊だけでなく、大阪、岡山や鹿児島など遠方からの参加があり、理科教育に対する関心の深さを示しているといえるであろう。交通渋滞のために有馬文部大臣が30分遅れて到着というハプニングがあったが、統計データを用い大変説得力ある明快な講演であり、10分の質疑応答では足りないほど多くの質問がなされた。パネルディスカッションでは、フロアーからの参加者も交え、青少年の理工系離れが問題となっている現状に対して、今後の理科教育のあり方などについて様々な視点から活発な討論が行われた。また、今回のシンポジウムを通して科学教育に対するネットワークを広げることができ、有意義なシンポジウムであったといえるであろう。
(第2部 大島まり)
第12回生研学術講演会が3月26日に開催された。今回は、学会・産業界・海外のITS(Intelligent Transportation Systems)研究の指導者を講師として招き、研究の現状、今後の課題、研究戦略とくに産官学連携のあり方などをさまざまな視点から分析し、その将来像を探る試みがなされた。吉本堅一教授(東京大学大学院工学系研究科)の「機械関係におけるITS研究内容」、池内克史教授(本所第3部)の「電気関係におけるITS研究内容」、桑原雅夫助教授(本所第5部)の「土木関係におけるITS研究内容」、保坂明夫氏(AHS研究組合)の「自動車メーカーの取り組み」、福井良太郎氏(沖電気工業(株))の「電機メーカーの取り組み」、Charles Thorpe教授(カーネギーメロン大学ロボティクス研究所)の「カーネギーメロン大学における取り組み」、正木一郎教授(MITマイクロシステムズ・テクノロジー研究所)の「MITにおける取り組み」、Alberto Broggi教授(パドバ大学情報科学科)の「パドバ大学における取り組み」、坂内正夫教授(本所所長)の「ITSの開発・実用化における産官学連携の取り組み」の各講演が行われた。当日は、約150名の聴衆が集まるほどの盛況で、今回のテーマに対する関心の高さがうかがわれた。
(広報委員長 藤田隆史)
海は地球環境に大きな影響を与えていますが、海中や海底を高い頻度で広い範囲に観測することは容易ではありません。われわれは海中の僅かな部分を垣間見ているに過ぎないのです。状況を打開するには、何らかの新しい画期的な海中観測プラットフォームが必要です。このような観点から、本所では1984年から研究グループを形成し、自律型海中ロボットの研究開発を続けてきました。研究プロジェクトの成果の一例として、閉鎖式ディーゼル機関を搭載したアールワン・ロボットを開発し、太平洋で12時間にわたる長時間連続潜航をおこないました。こうした成果を踏まえて、1999年4月より10年間の時限で「海中工学研究センター」が設置されました。自律型海中ロボットの研究開発を中心とした海中観測プラットフォームの研究開発をおこなうとともに、国内外の研究の推進と連携に努めていきます。
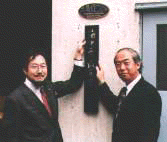
設立当初の陣容は、浦研究室、藤井(輝)研究室、林(昌)研究室、高川(客員教授)研究室です。
(海中工学研究センター長 浦 環)
平成11年度の東京大学職員永年勤続者表彰式が4月12日に山上会館で行われ、蓮實重彦総長の祝辞の後、本年度被表彰者68名を代表し西堀わか子さん(研究協力部国際交流課)に表彰状と記念品が授与され、また、榮木実枝さん(医学部附属病院)が謝辞を述べた。
引き続き催された祝賀会では、坂内所長、井手ノ上事務部長を交えて、それぞれの20年間を思い語りつつ、和やかなうちに散会した。なお、本所の被表彰者は下記のとおり。
事務部 文部技官 経理課施設主任 小松崎 丈夫
事務部 文部事務官 経理課施設掛主任 安室 早苗
事務部 文部技官 経理課施設掛主任 山上 幹夫
事務部 文部技官 経理課施設掛建築主任 酒井 清武
(人事掛長 小池嘉弘)

駒場新キャンパスへの移転も研究室の移動が進み、既に昨年度中に第I期研究棟(C棟)の約7割が入居を済ませていますが、移動後間もないということもあり、未だ六本木、駒場の二重生活という場合も多い様です。研究室の移動につきましては、これで当面一段落となり、今後は今年度後半に第1部、第5部の残りの研究室の移動が実施される予定となっています。
同じく第I期工事分として建設が進められておりました国際・産学共同研究センター棟は、6月の入居開始に向けての準備が行われている状況で、キャンパス構想の中「開かれた大学」を目指した交流活動の中核として、同センターの役割が期待されるところです。第II期工事分(B棟)につきましては、4月末迄に建物を覆っていた足場も撤去され、隣接するC棟に続きその全容を現し、今後内装工事から仕上げと、今夏に予定されている竣工に向けての作業が進められます。また、これに伴いB棟側からC棟への機器搬入が可能となるため、これまで搬入経路に制約の有った大型の機器も設置できることになりました。
第III期工事分(D棟)に関しましては、基礎部分の工事が完了し現在鉄骨の組み上げ作業が順調に進められています。さらに、第IV期工事分(E、F棟)につきましては3月に工事発注が行われ、設計の細部について調整が行われている状況です。
付属施設関係でも、先に竣工の運びとなった設備センターにおいて受電の切り替えに向けての準備が行われる等、着々と改善の作業が進められています。一方、今年度中には生研各棟周辺の通路、植え込みといった環境の整備も行われる予定になっており次第にキャンパスらしい趣を備えて行くことでしょう。
研究室移動の本格化に伴い、これまで主体であった建物、設備といったハード面の整備に対し、事務処理・保守管理体制といったソフト面の整備が今後重要になって来ることと思われます。既に、事務職員の常時3人体制の実施、六本木駒場地区間連絡便の1日1往復から2往復への増便、清掃の業者委託等が実施されていますが 、今後この面での一層の充実を図るとともに皆様のご協力を頂きたくお願い申し上げます。

第1部 教授 田中 肇
生研に着任してちょうど10年が経過しました。この間、高分子・液晶・コロイド・せっけん分子系など、ソフトマテリアル・複雑流体と総称される物質群の物理的性質と、光の場とこれらの系との結合に焦点を当てて研究してきました。最近では、興味はさらに広がり、「水の密度がなぜ4℃で最大になるのか」、「液体はなぜガラス状態になるのか」といった基本的な問題に興味をもち、「液体は物理的にどう記述すべきか」という問いに答えるべく研究を行っています。本年度から駒場での新生活もはじまり、身の回りの環境も大きく変わりましたが、柔軟な発想を大事にして独創性の高い研究を進めるよう努力していきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
第5部 教授 加藤信介
この4月に昇任させていただきました。生研にはかれこれ18年間お世話になりました。恵まれた研究環境に甘えてやりたい放題やって来ました。専門は、居住に関わる物理的な環境の計測、評価、設計方法論であります。熱や流れといった因果関係の明確な事象に、人間の感性という不可解な要素を包含させることが、今の私の大きなテーマの一つです。環境の持続可能性は、エネルギー多消費型の現在社会にとって利便性、快適性を損なう脅威ともなり、その達成には抵抗が予想されます。感性を上手に利用して、快適性を損なわずエネルギー消費を押さえる工夫が必要です。戦略性を持って精進し、広く学内、社会に貢献するよう努力いたしたいと思っております。
第2部 助教授 大島まり
4月1日付で、助教授に昇任いたしました。主に有限要素法を適用したLarge Eddy Simulationの乱流解析を中心とした研究をしておりましたが、最近は、新たな研究分野として血流の数値シミュレーションに取りかかっています。今後は実験など新しいことに挑戦しながら、今まで培ってきた知識と経験を生かして、生体計算力学の分野を研究していきたいと考えています。また、社会貢献の一環として行ってきているSNG(Scientists for the Next Generation)についても、今後さらに発展できるよう力を注いでいきたいと思います。
本年度は筑波大学との併任となり、筑波と東京の往復と忙しい年となりそうです。2つの大学を経験できる良い機会ですので、視野を広めることのできる有意義な経験となるようがんばりたいと思います。
どうぞ、よろしくご指導の程お願い申し上げます。
第2部 助教授 白樫 了
4月1日付で助教授に昇任させて頂きました二部の白樫です.現在,研究の柱として,大きく分けてバイオとエネルギーをたてております.具体的には,生命体としての人間を支える医療と食料,その集団である社会の基盤の一つであるエネルギー利用と変換機器について研究をおこなっていこうと考えております.目下のところ,細胞を含む移植用の生体の長期保存法の開発に力を入れておりますが,徐々にその他のテーマにも力点をかけていこうと考えています.常々,生研の教官・職員の皆様には多大なる御世話を頂いておりますが,これからも何かと御面倒をおかけするかと存じますので,その折はどうか宜しく御願い申し上げます.
第5部 助教授 アンナ プライス
私の生研における2年間は非常にすばらしい体験でした。私はミュンヘン技術大学やストックホルム大学に滞在したことがあり、今でも懐かしく思い出されます。しかし、生研ほど居心地が良く、親切で、しかも、しっかりした研究体制が整っていて、実り多い議論や打ち解けた研究交流を楽しめたところはありませんでした。そのおかげで、かつてなかったほどの効率で、東京における研究成果をあげることができました。こうした私の東京に対する好印象は橘秀樹先生のお世話とご厚意の賜物です。本当に感謝したいと思います。もちろん、生研のスタッフのみなさんからも非常に良くしていただきました。日本に関しては決して薄れることのないであろう良い想い出しかありません。みなさんどうもありがとうございました。
(訳 沖 大幹)
第4部 講師 亀井雅之
科学技術庁の無機材質研究所に4月1日付で転任致しました。皆様にきちんとご挨拶申し上げる間もなく異動致しましたことを心よりお詫び申し上げます。生産技術研究所には平成9年の4月16日から2年間お世話になりました。口の悪い友人に「Touch and go」などと冷やかされておりますが、私自身の実感としては、短くはありましたが楽しく充実した時間に満ちた至福の2年間でした。今後文部省と科技庁は統合へと進んでゆくとのこと、何かとお世話になることが多いかと存じます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
第2部 客員教授 高川真一
この度,海中工学研究センター客員教授に就任しました,海洋科学技術センターの高川 真一です.
「鉄腕アトム」という漫画を多くの方はご存じだと思いますが,海中工学研究センター長の浦 環 教授と共に,「鉄腕アトム」を目指しつつ,まだよちよち歩きの自律型海中ロボットを大きく成長させるために,世界の研究者と協力して研究が遂行できるような体制を作っていきたいと考えています.
海洋科学技術センターでは大深度潜水艇の開発や地球内部を探査する掘削船の開発に携わっておりますが,自律型海中ロボットも含めて,これらの新技術・工学は関係者以外ほとんど理解されていないのが実状です.研究の遂行と併せて関係者以外にも理解されるような情報の発信にも努力したいと考えています.
第2部 助教授 藤井輝夫
今年度、新たに設置された海中工学研究センターの助教授として、4年ぶりに生研に戻って参りました。4年前まで、大学院生として5年間、教官として2年間を生研で過ごし、主として自律海中ロボットの研究をしておりましたが、最近は、マイクロチップを用いた生化学反応や分析、細胞のパターニングなど、着任前の理化学研究所時代に立ち上げた新しいテーマも展開しています。海中工学センターでは、既存の枠組みにとらわれない生研の良さを体現すべく、こうした新技術とロボット技術との融合によって、ユニークな探査システムの研究開発を進めたいと考えております。今後ともよろしくご指導の程お願い申し上げます。
第4部 助教授 畑中研一
平成11年4月1日付で生研第4部の助教授として東京工業大学生命理工学部より転任して参りました。生研には昭和58年10月から平成元年6月まで助手として勤務しておりましたので懐かしい思いもあります。専門は糖質工学を中心とした生化学と高分子合成化学であり、機能性糖鎖分子の設計・合成、人工の糖質化合物を用いた細胞接着基質の開発や細胞機能制御、医療への応用などに関する研究を行う予定です。これまで行ってきた生命科学や合成化学の研究を生かして、物資生産や医療装置開発といった観点から細胞やポリマーと対面していきたいと考えております。何卒宜しくお願い申し上げます。
第5部 講師 坂本慎一
4月1日付で第5部の講師として生研スタッフの末席に加えていただきました。専門は建築音響・騒音制御で、特に室内・屋外での音の伝搬や音の分布を予測するための数値シミュレーション法の開発に興味をもって研究を行っています。大学4年生の時に卒業研究で生研にお世話になって以来9年間、恵まれた研究環境のもとで自由に研究を行わせていただきました。今後は、生研の充実した研究環境に恥じないような研究を、特に「社会の役に立つ」研究を念頭に置きながら、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
事務部 経理課長 真取秀明
平成11年4月1日付、人事異動により、教養学部等事務部から生産技術研究所の事務部経理課に参りました。
生産技術研究所は平成10年度から、住み慣れた六本木地区から駒場Ⅱ地区へ移転が始まっているとのことで、急遽移転先へ案内して頂きました。
C棟の完成に伴っての移転とB棟以下の建築工事が急ピッチで進められていて、これらの建物が完成し,また移転も完了したら駒場Ⅱ地区は、大所帯(生研・国際産学・先端研等)な研究・教育の場となると思われます。そして、それに伴って生研の事務部も新しい時代を迎え、合同事務部として先生方へのサポートをしていかなければならないと思います。まだ、ちょっと先の事とは思いますが、今後とも生研の一員として宜しくお願い申し上げます。
生研ニュースホームページへ
教職員
第2部 助教授 須田義大、技術官 小峰久直、元大学院学生 岩佐崇史、研究員 曄道佳明
受賞日:1999.3.18
受賞名(団体名):Dynamics and Design Conference`99
第2回「運動・振動・波動の世界」映像・マルチメディアコンテスト 映像賞・最優秀賞
(日本機械学会 機械力学・計測制御部門)
受賞項目:コルゲーションの発生・成長現象の可視化
第5部 教授 浦 環、受託研究員 小原敬史
受賞日:1999.4.5
受賞名(団体名):日本機械学会賞(技術賞)(日本機械学会)
受賞項目:自律型海中ロボットの開発
第2部 助教授 白樫 了
受賞日:1999.4.5
受賞名(団体名):日本機械学会賞奨励賞 日本機械学会
受賞項目:生体材料に対する凍結保護物質の浸透に関わる物性値の研究
学生
第5部 安岡・柴崎研 大学院学生 中川 愛
受賞日:1998.11.20
受賞名(団体名):優秀講演者 ((社)土木学会)
受賞項目:論文「満足度調査に基づいた地域生活指標に関する研究」
生研ニュースホームページへ
平成10年11月13日、セクシュアル・ハラスメント防止等に関し、人事院規則10-10が制定されました。生研においては、相談窓口を下記にて開設いたします。職員のみならず、非常勤職員、学生、男女を問わず、お悩みの方は気軽にお声をかけてください。
セクシュアル・ハラスメントをしないようにするためには、職員の一人一人が次の事項の重要性について十分認識しなければなりません。
<意識の重要性>
1.お互いの人格を尊重しあうこと。
2.お互いが大切なパートナーであるという意識を持つこと。
3.相手を性的な関心の対象としてのみ見る意識をなくすこと。
4.女性を劣った性として見る意識をなくすこと。
<相談員>
坂内所長 電話 2000
E-mail s-director@iis.u-tokyo.ac.jp
佐藤総務課長 電話 2002
〃 satokuni@iis.u-tokyo.ac.jp
武原研究担当専門職員 電話 2024 〃
take@cc.iis.u-tokyo.ac.jp
来る6月3日(木)・4日(金)の2日間は生産技術研究所の公開です。
例年通り、100近い研究室の公開や研究グループの紹介と講演会を行います。また、本年は初日に本所創立50周年の記念講演会も行われます。
講演会の講師と題目は下記の通りです。
6月3日(木) 15:00~17:00 創立50周年記念講演会
15:05~
生研半世紀の回顧と展望
尾上 守夫((株)リコー中央研究所技術最高顧問)
16:00~
半導体と量子力学 -物理学者が歩んだ50年の道-
江崎 玲央奈((財)茨城県科学技術振興財団理事長)
6月4日(金) 11:00~11:50
「真空」から生まれるもの
第1部 岡野 達雄 教授
13:00~13:50
計算固体力学の発展
第2部 都井 裕 教授
14:10~15:00
仮想現実感モデルの自動生成
第3部 池内 克史 教授
第1部 黒田研 的場 修
第4部 迫田研究室
ゼロエミッションという言葉が最近ではマスコミ等でもよく使われるようになってきた。ゼロエミッションとは、ある生産プロセスでの無用の排出物を別の生産プロセスの原材料として循環利用すれば、いわゆる「廃棄物ゼロ」が実現できると国連大学が5年前に提唱した産業システムの概念・哲学であり、21世紀において持続可能な発展を続けるためには必須であることには疑問の余地はないであろう。しかしながら、農業等を産業基盤とする発展途上国とは異なり、我国のように工業国としての産業構造が既に出来上がっている場合には、ゼロエミッション社会の実現は容易ではない。この問題への工学の貢献のひとつは、現状の各種産業から排出されている未利用素材を価値のある資源へと変換する技術の開発であると考え、標記の研究を行っている。
高温高圧水は特異的な反応場となる。このことに着目して植物バイオマス系の未利用素材(古紙、廃木材、もみ殻、ビール等の絞り粕、などなど)を工業原料となる化学物質に変換するプロセスの開発に当面は的を絞っている。植物バイオマス系素材は、主にセルロース、ヘミセルロースおよびリグニンの3成分にて構成される。高温高圧水処理を施すことで、図に示したようにセルロースやヘミセルロースからは加水分解により糖類が生成し、さらに糖類の二次分解でフルフラール類や有機酸などが生成する。また、リグニンの一部は可溶性リグニンとして回収できる。これらの反応が起こる温度領域はそれぞれ異なっており、反応温度の工夫や分離操作の組込みなどによって素材の大部分を有価物に変換することも可能であろう。また、このような処理は大量の未利用素材を対象とすることが前提となることから、連続反応装置の設計・開発や蒸煮爆砕法と呼ばれる既存技術との組合せなどの研究も並行して行っている。
この研究課題は未だ第1歩を踏み出した段階にある。今後は、この高温高圧水処理などの物理化学的な変換技術のみでなく、生物的変換技術やこれら両者の融合プロセスの実用化に向かっていくことを考えている。

今年度から生研ニュース部会のメンバーになり、最初から編集担当ということで多少の不安とともに作業を始めました。ところがいざ始めてみると、他の部会員の方々にも助けて頂きながら、以外と順調に発行にこぎつけそうでほっと一息ついているところです。ところで、これまでは何気なく目を通してきたこの生研ニュースですが、実は発行部数4000を越え広く所内外に配布されているメディアであり、生研における様々な活動を伝える重要な役割を果たしていることを知りました。これからも皆様からのお声をもとに更に魅力ある紙面とすべく努力していきたいと思います。
(佐藤洋一)