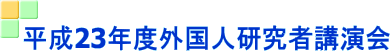
外国人研究者の学術講演会を開催しています。
開催場所のMAPは、こちらから
外国人研究者講演会参加費
賛助員は無料
外国人研究者講演会申込方法
事前にお申込みください。
(研究室に連絡された場合、事前申込は不要です。)
財団法人生産技術研究奨励会 事務局
e-mail :fpis@interlink.or.jp
Fax : 03-5738-5224
【第801回】
●日 時
平成24年3月7日(水)13:50~14:40
●場 所
東京大学生産技術研究所 第3会議室(Fw701)
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
小田急線 東北沢駅 徒歩7分
小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
●講演者
Dr. Swetlana Schauermann
Postdoctoral Research Associate, The Fritz-Haber-Institute, German
●テーマ及び講演内容
NTERACTION OF GAS PHASE MOLECULES WITH NANOSTRUCTURED MODEL
SUPPORTEDCATALYSTS: THERMODYNAMICS AND KINETICS
-ナノ構造モデル触媒と分子との相互作用-
金属ナノクラスターは、触媒のモデル物質として注目を集める。本講演では、ナノクラスターに
おける水素化反応のキネティクスとダイナミクスを多ビーム分子線と赤外吸収分光で調べた
結果を議論する。
●司会者
東京大学 教授 福谷克之
【第800回】
●日 時
平成24年3月2日(金)15:00~16:30
●場 所
東京大学生産技術研究所 中セミナー室3(As303・304)
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
小田急線 東北沢駅 徒歩7分
小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
●講演者
Prof. Marian Paluch
Institute of Physics, University of Silesia, Poland
●テーマ及び講演内容
MOLECULAR MOBILITY AS A KEY FACTOR IN CONTROLLING PHYSICAL STABILITY
OF AMORPHOUS DRUG: CELECOXIB.
広帯域誘電分光法を用いて、セレコキシブの過冷却状態、ガラス状態における分子運動の
温度依存性について研究を行った。その結果、貯蔵条件である室温における構造緩和率が
室温での非晶質からの再結晶化率に一致することを見出した。このことは、非晶質の結晶化
に対する安定性が、構造緩和過程で支配されていることを示唆する。ベータ緩和の寄与も含め、
非晶質の安定性について議論する。
●司会者
東京大学 教授 田中肇
【第799回】
●日 時
平成24年2月23日(木) 15:40~17:10
●場 所
東京大学生産技術研究所 中セミナー室3(As303・304)
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
小田急線 東北沢駅 徒歩7分
小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
●講演者
Prof. Julia M. Yeomans
The RudolfPeierls Centre for Theoretical Physics, University of Oxford, United Kingdom
●テーマ及び講演内容
SWIMMING AND SCATTERING AT LOW REYNOLDS NUMBER
バクテリアに代表される微小遊泳体の泳動は、そのサイズから低レイノルズ領域にあり
ストークス近似が成り立つと考えられる。これは時間反転対称性の存在を示唆するが、
このような情況でどのように泳動がなされるかについて泳動運動の対称性、遊泳体間の
流体力学的相互作用などを中心に数値シミュレーション、理論の結果をもとに考察する。
●司会者
東京大学 教授 田中肇
【第798回】
●日 時
平成24年2月2月23日(木) 14:00~15:30
●場 所
東京大学生産技術研究所 中セミナー室3(As303・304)
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
小田急線 東北沢駅 徒歩7分
小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
●講演者
Prof. Daniel Bonn
Statistical Physics Laboratory, Ecole Normale Superieure, France
●テーマ及び講演内容
EXPERIMENTAL MEASUREMENT OF THE FREE ENERGY OF SOLIDS, LIQUIDS
AND GLASSES
剛体球コロイド系の自由エネルギーを直接求める新しい手法を紹介する。本手法は、
高体積分率の系にも利用でき、自由エネルギーは共焦点顕微鏡で得た粒子座標から
求まる自由体積を用いて計算される。ガラスのエイジング過程では、より低い結晶状態の
自由エネルギーへの推移が確認できた。
●司会者
東京大学 教授 田中肇
【第797回】
●日 時
平成24年2月17日(金)15:00~16:30
●場 所
東京大学生産技術研究所 中セミナー室3(As303・304)
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
小田急線 東北沢駅 徒歩7分
小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
●講演者
Prof. Slobodan Zumer
Faculty of Mathematics and Physics, University of Ljubljana & Jozef Stefan
Institute, Slovenia
●テーマ及び講演内容
COLLOIDAL AND CONFINED BLUE PHASES
コレステリックブルー相(BP相)は、線欠陥と2重ねじれ円筒が規則的に配列した複雑な
3次元秩序構造を持つ。講演では、バルク、および空間拘束下のBP相にコロイド粒子を
分散した系の示すエキゾチックな構造とその制御、さらには光学的な応用について触
れる。
●司会者
東京大学 教授 田中肇
【第796回】
●日 時
平成24年2月15日(水)11:00~12:00
●場 所
東京大学生産技術研究所 小セミナー室1(An403)
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
小田急線 東北沢駅 徒歩7分
小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
●講演者
Dr. Valentin Golosov
Principal Scientific Researcher, Laboratory for Soil Erosion and Fluvial Processes,
Faculty of Geography, Lomonosov Moscow State University, Russian Federation
●テーマ及び講演内容
SIGNATURE OF FLOW AND RELAXATION EVENTS IN GLASSES AND SUPERCOOLED
LIQUIDS
137CS REDISTRIBUTION AFTER CHERNOBYL INCIDENT: RUSSIAN EXPERIENCE
‐チェルノブイリ事故後のCs-137の再分布 : ロシアの事例‐
ロシア平原のチェルノブイリ原発事故による汚染レベルが異なる地域において、事故直後の
Cs-137降下の特徴を明らかにした。主に、地表に降下したCs-137が、河川システムのなかで
どのように再移動するかということに主眼を置いて分析を行った。ロシア平原の様々な場所で、
耕作地斜面と小流域におけるCs-137の再移動の調査結果を示した。また、チェルノブイリ
由来のCs-137による生態系への短期、中期、そして長期的な影響について考察をおこなった。
●司会者
東京大学 教授 沖大幹
【第795回】
●日 時
平成24年2月13日(月)15:00~16:30
●場 所
東京大学生産技術研究所 中セミナー室3(As303・304)
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
小田急線 東北沢駅 徒歩7分
小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
●講演者
Prof. Anael Lemaitre
Navier Institute, East Paris University , France
●テーマ及び講演内容
SIGNATURE OF FLOW AND RELAXATION EVENTS IN GLASSES AND SUPERCOOLED
LIQUIDS
ガラス転移点近傍の流体におけるニュートン・非ニュートン的挙動の遷移について議論する。
講演ではこの遷移の起源が外部剪断と熱揺らぎによるそれぞれの変形機構の時間スケール
のクロスオーバーによって記述されることを示す。
●司会者
東京大学 教授 田中肇
【第794回】
●日 時
平成24年1月23日(月)14:00~15:00
●場 所
東京大学生産技術研究所 小セミナー室1(An403)
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
小田急線 東北沢駅 徒歩7分
小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
●講演者
Dr. Robert. RUBINSTEIN
Senior Research Scientist, NASA Langley Research Center, USA
●テーマ及び講演内容
‘REAL’ TURBULENCE AND ‘IDEAL’ TURBULENCE
コルモゴロフの理論によると、「現実」乱流は非一様で非等方なのもだが、局所的には
「理想」的すなわち一様で等方と見做せる、ということになっている。局所一様性が妥当
かどうかについて、密度変化する乱流の問題という文脈で議論する。局所一様性は重要
かつ有用だが、モデル化のためには非一様性乱流を扱う確かな理論が必要となる。
しかし応用という観点で、現存するクロージャの理論は複雑すぎる。ここでは簡略化した
クロージャを提案する。それによって、将来のモデル研究の進展に適した解析的理論に
到達できるかもしれない。
●司会者
東京大学 助教 横井喜充
【第793回】
●日 時
平成24年1月18日(水)10:00~11:30
●場 所
東京大学生産技術研究所 中セミナー室1(An401・402)
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
小田急線 東北沢駅 徒歩7分
小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
●講演者
Prof. Jan M. Rabaey
University of California at Berkeley, USA
●テーマ及び講演内容
THE SWARM AT THE EDGE OF THE CLOUD
日本は国内センサー販売数47億個(世界販売数170億個の中で)あると言われるセンサー
大国だが、この次に来る、スマート・コミュニティー世代、アンビエント・エレクトロニクス世代
へのシステム的なメッセージが多く含まれている。Rabaey先生は、センサーネットなどをいち
早く提唱するなどビジョナリーとして著名だが、今回はSwarm という概念で、個人や個々の
ものが動いて使えるリソースがダイナミックに変化するような新しい物質情報環境でのシス
テムOSのあり方などにも言及するものである。最新の取り組みや今後の挑戦について
ご講演を頂く。
●司会者
東京大学 教授 桜井貴康
【第792回】
●日 時
平成24年1月12日(木)15:00~17:30
●場 所
東京大学生産技術研究所 中セミナー室4(As311・312)
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
小田急線 東北沢駅 徒歩7分
小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
●講演者
Dr. Don Choi
Associate Professor, California Institute of Technology, USA
●テーマ及び講演内容
TOWARDS NEW PERSPECTIVES ON THE ARCHITECTURAL HISTORY OF MODERN JAPAN
-日本の近代建築史学の再見へ-
日本の近代建築史研究が20世紀後半に完熟したとすれば、21世紀にはどの方向へ進化して
いくのか。本研究の目的はアメリカにおける建築史学の現代的傾向を基礎にし、いわゆる
「ミレニアム世代」の特質や英語圏読者のニーズを考慮しながら海外向きの近代建築史の
新視点を展開することである。
●司会者
東京大学 教授 村松伸
【第791回】
●日 時
平成23年12月5日(月)14:00~15:30
●場 所
東京大学生産技術研究所 小セミナー室2(An404)
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
小田急線 東北沢駅 徒歩7分
小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
●講演者
Prof. Lydéric Bocquet
Condensed Matter Lab, University of Lyon , France
●テーマ及び講演内容
HETEROGENEITY AND COOPERATIVITY IN FLOWS OF SOFT GLASSY MATERIALS
エマルジョン、粉体、分子性ガラスなどに代表される非晶質のガラス状物質は、固体と
流体の間の複雑な流動挙動を示す。ここでは、このような流動の非局所性に焦点を当
て、実験・理論の両面から弾塑性変形のダイナミクス、シアバンドに伴う不均一化現象
などの機構に迫る。
●司会者
東京大学 教授 田中肇
【第790回】
●日 時
平成23年11月28日(月)16:00~17:00
●場 所
東京大学生産技術研究所 中セミナー室2(As301・302)
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
小田急線 東北沢駅 徒歩7分
小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
●講演者
Prof. Kirill. KUZANYAN
IZMIRAN, Russian Academy of Science, Russia
●テーマ及び講演内容
HELICAL PROPERTIES OF SOLAR MAGNETIC FIELDS AND SOLAR DYNAMO
太陽のダイナモ機構を研究するためのデータを示す。ダイナモ機構の重要な駆動因子は太陽磁場
のヘリシティ(ねじれ度)である。ヘリシティは乱流場の鏡映対称性からのずれを表す一般的な性質
である。太陽磁場の乱流としての性質を議論し、ヘリシティを計算するために利用可能なデータに
ついて概観する。データの解釈には系統的な方法が必要となる。ダイナモ機構や太陽の周期性に
関するさまざまな性質をよりよく理解するために、これらのデータをどのように用いるかを示す。
●司会者
東京大学 助教 横井喜充
【第789回】
●日 時
平成23年11月28日(月)14:30~15:30
●場 所
東京大学生産技術研究所 中セミナー室2(As301・302)
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
小田急線 東北沢駅 徒歩7分
小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
●講演者
Prof. Matthias. REMPEL
High Altitude Observatory, National Center for Atmospheric Research , USA
●テーマ及び講演内容
NUMERICAL SIMULATIONS OF SUNSPOTS: FROM THE SCALE OF FINE STRUCTURE TO
THE SCALE OF ACTIVE REGIONS
ここ5年で磁気対流黒点モデルは劇的な進歩を見せ、黒点全体のシミュレーションでも黒点の微
細構造を充分に解析できるようになった。最近の研究の簡単な概観を行った後、(1)太陽黒点の
微細構造に焦点を当てた現時点で最高の解像度の計算、(2)水平方向に50Mmを超えて広がる
計算領域についての数日にわたる時間発展を計算する低解像度の黒点モデル計算、(3)活動領
域のスケールについての黒点モデル、という三つの異なるクラスの数値的黒点モデルについて言及
する。
●司会者
東京大学 助教 横井喜充
【第788回】
●日 時
平成23年11月18日(金)10:30~12:00
●場 所
東京大学生産技術研究所 E棟ラウンジ(E棟2階)
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
小田急線 東北沢駅 徒歩7分
小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
●講演者
Dr. P. S. Mukherjee
Chief Scientist & Head, Advanced Materials
Technology Dept. CSIR-IMMT,India
●テーマ及び講演内容
THERMAL PLASMA PROCESSING OF INDUSTRIAL WASTES
(INCLUDING E-WASTE) FOR RECOVERING METAL VALUES
-熱プラズマを用いた(電気電子機器廃棄物を含む)産業廃棄物からの金属有価物の回収-
産業廃棄物には有価金属が含まれている場合が多く、特に電気電子機器廃棄物は都市鉱山
としても注目されているように多くの貴金属が含まれている。本講演では、種々のプラズマプロ
セスの研究紹介をはじめ、熱プラズマを用いたより高効率な回収方法の開発研究について紹介
を行う。
●司会者
東京大学 教授 森田一樹
【第787回】
●日 時
平成23年10月27日(木)15:00~16:00
●場 所
東京大学生産技術研究所 中セミナー室3(As303・304)
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
小田急線 東北沢駅 徒歩7分
小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
●講演者
岡 武史教授
シカゴ大学名誉教授 , 米国
●テーマ及び講演内容
ASTRONOMY AND CHEMISTRY
「天文学と化学」
星間空間での分子進化において、重要な役割を果たすH₃⁺イオンの探求を多年にわたって
研究されてきた成果を、講演者の研究者としての歩みと共に、わかりやすく解説していただ
く予定である。宇宙空間物理のみならず、固体表面科学やプラズマ応用科学などの分野で
仕事をされている方々の来聴を歓迎いたします。
●司会者
東京大学 教授 岡野達雄
【第786回】
●日 時
平成23年10月18日(火)15:00~16:30
●場 所
東京大学生産技術研究所 小セミナー室2(An404)
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
小田急線 東北沢駅 徒歩7分
小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
●講演者
Dr. Ranjini Bandyopadhyay
Associate Professor, Soft Condensed Matter Group, Raman Research Institute , India
●テーマ及び講演内容
EXPERIMENTS ON AGING SOFT COLLOIDAL GLASSES AND RISING BRAZIL NUTS
シア変形下のガラス状粘土コロイド溶液が示す力学的な2段緩和現象とエネルギーランド
スケープとの関係、擬2次元多分散駆動粉体系においてみられる境界に駆動された対流に
よるブラジルナッツ効果の二つのテーマについて議論する。
●司会者
東京大学 教授 田中肇
【第785回】
●日 時
平成23年7月20日(水)16:00~17:00
●場 所
東京大学生産技術研究所 大セミナー室(Dw601)
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
小田急線 東北沢駅 徒歩7分
小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
●講演者
Associate Prof. Alptekin AKSAN
Biostabilization Laboratory and Biopreservation Core Resource (BioCoR), Mechanical
Engineering Department & The BioTechnology Institute, University of Minnesota, USA
●テーマ及び講演内容
BIOSTABILIZATION & BIOTHERMODYNAMICS : THE STORY OF WATER
ー生体の安定化と生体熱力学:水の観点からー
自然界のある種の生物は、極度の高温や低温、乾燥環境の下でも生き延びることができる。
これらの生物は体内で保護物質を合成して細胞内外の水の熱力学的状態を変化させるこ
で、極限環境の耐性を獲得している。本講演では、生体が低温、乾燥、相変化をおこす際
の内部の水の状態を、特に水素結合ネットワークの変化に注目し、水、溶質、保護物質の
相互作用について論じる。
●司会者
東京大学 准教授 白樫了
【第784回】
●日 時
平成23年6月20日(月)10:30~12:00
●場 所
東京大学生産技術研究所 中セミナー室1(An401・402)
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
小田急線 東北沢駅 徒歩7分
小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
●講演者
Prof. David Blaauw
University of Michigan, USA
●テーマ及び講演内容
MILLIMETER SCALE SENSOR NODES DESIGN USING LOW VOLTAGE OPERATION
体積縮小を続けるコンピューターシステム。その先にあるmmスケールのセンサーノードを紹介
する。医療、監視、環境モニタなどの新しい応用分野を拓くこのシステムの実現上の壁は消費
電力であるが、これを解決するために低電圧動作(300-400mV)のアプローチをとった。センサ
プロセッサ等の極低消費電力設計を紹介し、1mm^3センサーノード設計に込められた障害と前
進を議論する。
●司会者
東京大学 教授 桜井貴康
【第783回】
●日 時
平成23年6月8日(木)10:00~11:30
●場 所
東京大学生産技術研究所 羽田野研究室セミナー室(Bw-801)
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
小田急線 東北沢駅 徒歩7分
小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
●講演者
Prof. Gonzalo Ordonez
Department of Physics and Astronomy, Butler University, USA
●テーマ及び講演内容
BOUND STATES IN THE CONTINUUM IN A TWO-ELECTRON SYSTEM
本来なら散乱されるエネルギーを持つ電子を、2つの壁の間の干渉によりトラップできることが知られ
ており、Bound State in the Continuum(BIC)と呼ばれています。本講演では、相互作用のある電子
系にこの概念を拡張します。様々な議論により、クーロン反発があっても2電子をまとめてトラップ
できることを示します。
●司会者
東京大学 准教授 羽田野直道
【第782回】
●日 時
平成23年6月3日(金)15:30~17:00
●場 所
東京大学生産技術研究所 小会議室2(An406)
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分
小田急線 東北沢駅 徒歩7分
小田急線・地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
●講演者
Prof. Grzegorz Szamel
Department of Chemistry, Colorado State University, USA
●テーマ及び講演内容
SPATIAL EXTENT OF DYNAMIC HETEROGENEITY IN A GLASSY HARD SPHERE SYSTEM
ガラス転移点近傍での、過冷却液体中の動的不均一性の発達が遅いダイナミクスの起源との
関連で注目されている。講演では、新しい方法で剛体球液体系の動的相関長と感受率の体積
分率依存性を研究した結果を報告する。
●司会者
東京大学 教授 田中肇