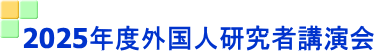
外国人研究者の学術講演会を開催しています。
■場 所
東京大学生産技術研究所
東京都目黒区駒場4-6-1 駒場IIキャンパス(駒場リサーチキャンパス)
千葉実験所
柏市柏の葉5-1-5
東京大学生産技術研究所 先端科学技術研究センター
東京大学(本郷)
■外国人研究者講演会参加費
賛助員は無料
■外国人研究者講演会申込方法
事前にお申込みください。
(研究室に連絡された場合、事前申込は不要です。)
一般財団法人生産技術研究奨励会 事務局
e-mail :fpis@interlink.or.jp
【第1117回】
●日 時
2025年7月14日(月)16:00~17:00
●場 所
東京大学生産技術研究所 中セミナー室5(As313・314)
●講演者
Associate Prof. Wonkeun hang
Nanyang Technological University, Singapore
Hollow-core optical fibers : Unlocking new regimes of light-matter
-中空コア光ファイバー:光と物質の相互作用の新領域-
中空コア光ファイバー技術の近年の進展により、これまで実現不可能だった方法で
光
従来の光ファイバーとは異なり、中空コアファイバーは中空の空洞を通して光を導く
構造を
相互作
可能となる。(ii)中
相互作用を長距離にわたって増強
調整可能となる。
これらの特性により、中空コアファイバーは多様な用途に対応可能なプラットフォー
として
本講演では、中空コアファイバー技術の最近の進展を概観し、我々の研究成果を
紹介
【第1116回】
●日 時
2025年7月11日(金)15:15~15:45
●場 所
東京大学生産技術研究所 An棟大会議室(An301・302)
●講演者
Prof. Mon-Shu HO
National Chung Hsing University, Taiwan
C84 Fullerenes on Si(111) : Toward Multiferroic Memory Devices
-Si(111)上のC84フラーレンの配列とマルチフェロイックメモリデバイスへの展望-
C84フラーレンをSi(111)-7×7上に成膜し、STMで約3.7eVのバンドギャップを
確認した。MFM・PEMにより強磁性と強誘電性を観測、DFT計算で外部電場
による
され、ReRAMや
【第1115回】
●日 時
2025年7月11日(金)14:00~14:30
●場 所
東京大学生産技術研究所 An棟大会議室(An301・302)
●講演者
Associate Prof. Chun-Liang LIN
National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan
Defect Engineering and Methanol
Decomposition on PtTe2 and PdTe2
-PtTe2およびPdTe2における欠陥制御とメタノール分解反応-
表面欠陥がメタノール分解反応を著しく促進することを示した。
反応確率はPtTe2で90%以上、PdTe2で40%以上に達し、触媒活性と
選択性は
【第1114回】
●日 時
2025年7月11日(金)11:00~11:30
●場 所
東京大学生産技術研究所 An棟大会議室(An301・302)
●講演者
Prof. Kimitoshi KONO
National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan
Hydrogen atoms meet electrons on the
surface of superfluid 4He
-超流動^4He表面における水素原子と電子の相互作用-
超流動^4He表面上の二次元電子系(SSE)と表面束縛状態の水素原子を共存させ、
極低温下でH原子と電子の化学反応による負水素イオン生成を観測した。
反応速度の温度依存性から、H原子2個と電子1個の三体反応であることを示し
【第1113回】
●日 時
2025年6月30日(月)14:00~16:00
●場 所
東京大学生産技術研究所 E棟ラウンジ(E棟2階)
●講演者
Prof. Bingbing San
Hohai University, College of Civil and Transportation Engineering, China
Mechanical behavior and optimization of
additively manufactured metal
structural components
-金属積層造形による構造材の力学的挙動と構造最適化の実践-
積層造形(AM)は、低炭素・DX等の土木工学における課題に対する革新的技術であ
本講演では、構造工学における金属積層造形(MAM)の応用について、MAMで
された構造部品の力学的挙動、およびMAMに適用される構造最適化手法と
である複雑な幾何形状をもつ部材の優位性を明らかにする。
【第1112回】
●日 時
2025年6月4日(水)16:00~17:00
●場 所
東京大学生産技術研究所 中セミナー室3(As303・304)
●講演者
Dr. G. Dan Pantoș
Senior Lecturer, University of Bath, Department of Chemistry, UK
Chiral emissive thin films and
J-aggregates
-キラル発光特性を持つ薄膜とJ会合体-
円偏光発光を持つ物質は光化学のみならず、応用物理や構造有機化学など
幅広い分野で
ヘリセノイド化合物とその薄膜
【第1111回】
●日 時
2025年5月22日(木)16:00~17:00
●場 所
東京大学生産技術研究所 中セミナー室3(As303・304)
●講演者
Prof. Pavel Anzenbacher Jr.
Director of the Center for Photochemical Sciences at
Bowling Green State University, USA
One Ring to Rule Them All:
Self-Organizing Receptors and Sensors
for Phosphate Anions
- すべてを支配するひとつの環状構造:リン酸アニオンを検出するための
本講演では、自己組織化したレセプタとセンサの設計に焦点を当てた最近の
取り組みについて議論する。化学センサは、標的種との結合とそのシグナル伝達に
由来する化学情報を可視化する役割を果たす。かつては、レセプタとそれに対応する
センサは、酵素と基質間の特異的な相互作用に着想を得た「鍵と鍵穴の理論」に
基づき設計されてきた。このアプローチでは、微量の標的種を高選択的に検出する
目的においては適しているが、重要な制約が存在する。それは、各標的種に対する
選択的なセンサが必要であり(1対1の制約)、未知の標的種に対しては適用できない
(外挿ができない)。この制約と選択的センサの合成に伴う課題を克服するために、
講演者は複数の交差反応性(選択性の低い)センサ素子からなるアレイを用いてい
従来の考え方では、このようなアレイは、センサの低選択性により、アレイを
センサ数を増やす必要があると考えられている。それに対して本講演では、
妥当性、そして「1対1」の制約から抜け出す方法について提案する。
リン酸の構造を有する多くの分析対象物が、異なる化合物として
同じ化合物の異なる濃度として定義されるか、あるいは混合物中の
割合として定義されるかを区別できるセンサの設計方法について
【第1110回】
●日 時
2025年5月21日(水)14:00~16:00
●場 所
東京大学生産技術研究所 第2会議室(C棟2F笠岡ラウンジ内)
●講演者
Prof. Harald Kloft
Structural design at Technische Universität Braunschweig, Germany
The Interaction of Material, Process and Form in Additive Manufactured
Construction
- 積層型建設法における材料・工法・形状の相互作用-
3Dプリントのような積層型建設法(AMC)は、構造設計・材料・工法を再定義し、
建設業界を大きく変革しようとしている。本講演では、AMCの根幹をなす電子制御
および計算機による設計について、特にそれらの動的な関係に焦点を当てながら
説明する。
【第1109回】
●日 時
2025年5月2日(金)14:00~15:00
●場 所
東京大学生産技術研究所 An棟大会議室(An301・302)
●講演者
Dr. Xuhai Xu
Assistant Professor, Columbia University, Dept of Biomedical Informatics,
Human-AI Ecosystems for Health and
Well-being
- 健康とWell-beingのための人間-AIエコシステム-
基本的な健康行動をモニタリングできるようになっています。インテリジェントな
健康モニタリングおよび介入のパイプラインというビジョンは、今や手の届くところ
あるように思えます。それでは、私たちはそこにどうたどり着けば良いのでしょう
紹介します。エンドユーザに対しては、行動科学の理論に基づく介入設計と汎用性の
行動モデルを橋渡しする我々の研究を紹介します。また、パッシブセンシングのデー
セット、人間中心のアルゴリズムおよび大規模言語モデル(LLM)、そしてエンド
専門家の双方にとってより堅牢で実用的な健康システムの実現を促進するベンチマー
プラットフォームの取り組みについても紹介します。