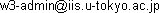| 連携研究センター |
|
センター長:加藤 千幸教授 計算科学技術連携研究センターは、今後予定されている大規模な計算科学技術の国家プロジェクトに対応し、我が国の計算科学技術用ソフトウェアの研究開発、人材の育成などを実施することを目的に、東京大学生産技術研究所が産業界や大学などと連携して設立されたものです。我が国の計算科学技術分野の広範な研究者、技術者を結集し、計算科学技術の発展に貢献することを目指します。 本連携研究センターでは、これまでの研究活動を踏まえ、次の様な戦略ソフトウェアの開発プロジェクトに着手しています。
|
| ナノエレクトロニクス連携研究センター | ||
|
センター長:荒川 泰彦教授 いつでも、どこでも、誰とでも、何とでもコミュニケーションが可能なユビキタス情報社会に向けて、安全で信頼性の高い超ブロードバンドネットワークシステムの構築のために、次世代の情報光電子デバイスを重点的に開発することが強く望まれています。 本研究センターでは、半導体ナノテクノロジーを中核技術として、次世代情報通信技術の基盤たるナノ光電子デバイス技術の研究開発を行い、ユビキタス情報技術の革新に向けた学術的基盤研究および社会への展開をはかります。特に,本センターにおいては、産学の英知を集約した強い連携のもとで研究プロジェクトを推進することにより、駒場リサーチキャンパスをナノエレクトロニクス研究の世界的拠点のひとつとすることをめざします なお、本研究センターは、先端科学技術研究センターと緊密な連携をはかりながら運営されます。 本センターの研究分野は下記のとおりです。
|
||
| 先進モビリティ(ITS)連携研究センター(ITSセンター) | ||
| センター長:池内 克史教授 広範な工学分野に渡り緊密な連携を特長とする生産技術研究所では、従来より都市・交通工学、電子・情報工学、機械・制御工学といった各分野の融合により、産官学協同によるITS研究の中心的存在として活動してきました。 先進モビリティ(ITS)連携研究センター(ITSセンター)は、そうした実績に基づき、さらにITS分野における国際連携の中心的拠点となることを使命として、平成17年より設置されました。 センターの中心的設備である、交通シミュレータ(TS)、運転シミュレータ(DS)、および最新の画像情報技術を融合した、複合現実感交通実験環境は,マクロからミクロまでマルチスケールの交通シミュレーションを可能とする、国内外においても他に例を見ない、各分野における最先端技術の結集と融合の象徴であり、それにより従来には不可能だった様々な仮想交通実験を可能としています。 平成17年からは、スイスEPFLに海外連携研究拠点をおくことをはじめ、欧米・アジアなど海外各国との国際連携を推進するとともに、従来より引き続き国内においても産官学連携の中心的拠点として活動を進めています。 |
TOP PAGE
Last Updated: 2002/10/21
Copyright(c) Institute of Industrial Science, The University of Tokyo